29の日は世田谷線に乗って♬「BISTRO Trois Quarts」
2013年 5 月05日(日)

 毎月29日を「肉の日」と呼んで楽しみにしている友人たちがいる。2人ともスカッシュ仲間。そしてFacebook仲間でもある。29日になると2人一緒に、あるいはそれぞれ別々に(毎月ほぼ確実に)肉料理の画像がサイトにアップされる。バリバリの肉食カップル。彼は見た目通りの、彼女は見た目とは大違いの大食漢で、大酒飲み。そんな2人とご一緒したい店があった。BISTRO Trois Quarts(ビストロ トロワキャール)。世田谷線の松陰神社前駅上りホームからなら徒歩1分、…も掛らない。駅至近の絶品肉料理の店。お誘いすると快諾。とある休日、体調万全に整えて「29の日ランチ」に臨んだ。
毎月29日を「肉の日」と呼んで楽しみにしている友人たちがいる。2人ともスカッシュ仲間。そしてFacebook仲間でもある。29日になると2人一緒に、あるいはそれぞれ別々に(毎月ほぼ確実に)肉料理の画像がサイトにアップされる。バリバリの肉食カップル。彼は見た目通りの、彼女は見た目とは大違いの大食漢で、大酒飲み。そんな2人とご一緒したい店があった。BISTRO Trois Quarts(ビストロ トロワキャール)。世田谷線の松陰神社前駅上りホームからなら徒歩1分、…も掛らない。駅至近の絶品肉料理の店。お誘いすると快諾。とある休日、体調万全に整えて「29の日ランチ」に臨んだ。

 「嬉しいっす♬」元野球少年の彼が目を輝かす。「楽しみにしてましたぁ♡」最近は乗馬が趣味だという彼女が微笑む。予約したのは、敢えて4人でカウンタ席。この店はキッチンとの距離が近く、シェフが近い。食事やお酒を楽しむだけではなく、シェフの調理の様子を眺められるカウンタ席がオススメ。次の一皿が出て来る前からライブで料理が楽しめる。まずはイノシシのリエット、白レバーのペーストとカシスソース。「うわぁ〜っ、美味しいっ」「これでワイン1本行けます!」焼きたてのパンとの組合せは幸せなマリアージュ。続いてキャロットラペ、サーモンなどの前菜が波状攻撃を掛ける。
「嬉しいっす♬」元野球少年の彼が目を輝かす。「楽しみにしてましたぁ♡」最近は乗馬が趣味だという彼女が微笑む。予約したのは、敢えて4人でカウンタ席。この店はキッチンとの距離が近く、シェフが近い。食事やお酒を楽しむだけではなく、シェフの調理の様子を眺められるカウンタ席がオススメ。次の一皿が出て来る前からライブで料理が楽しめる。まずはイノシシのリエット、白レバーのペーストとカシスソース。「うわぁ〜っ、美味しいっ」「これでワイン1本行けます!」焼きたてのパンとの組合せは幸せなマリアージュ。続いてキャロットラペ、サーモンなどの前菜が波状攻撃を掛ける。

 「わぁ〜っ、これやばいっすぅ〜」歓びに身もだえる彼。事前に「厚めに切りますか?」というシェフの聡ちゃんの挑発に乗った。「牛肩ロースのソテー レンズ豆の煮込み添え 粒マスタードソース」が、目の前にどかんと置かれる。ただでさえガッツリ系の店で肉増量とは。さすがだ。ワインも良いペースで飲み干される。うはは。清々しく気持の良いランチだ。「パンのお代わりはいかがですか」の問いにも「いただきます」と即答。小柄な彼女もよく食べ、よく飲み、よく笑う。飲んでいないはずのマダムのまゆみちゃん、お気楽妻の笑い声も重なる。愉しいランチだ。良い店だ。良い街だ。
「わぁ〜っ、これやばいっすぅ〜」歓びに身もだえる彼。事前に「厚めに切りますか?」というシェフの聡ちゃんの挑発に乗った。「牛肩ロースのソテー レンズ豆の煮込み添え 粒マスタードソース」が、目の前にどかんと置かれる。ただでさえガッツリ系の店で肉増量とは。さすがだ。ワインも良いペースで飲み干される。うはは。清々しく気持の良いランチだ。「パンのお代わりはいかがですか」の問いにも「いただきます」と即答。小柄な彼女もよく食べ、よく飲み、よく笑う。飲んでいないはずのマダムのまゆみちゃん、お気楽妻の笑い声も重なる。愉しいランチだ。良い店だ。良い街だ。
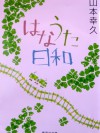
 山本幸久のデビュー作『笑う招き猫』2作目の『はなうた日和』は世田谷線沿線の街が舞台。2両だけの電車が軒先を掠めるように走る街々。この2作を読みながら、この店のすぐ下を通る電車を思い浮かべていた。のんびりと、ゆっくりと、温かな世田谷線。線路のすぐ横にはつくしが顔を出し、紫陽花などの花が咲く。母親に抱かれながら、じっと目を輝かせて電車を見入る幼子がいる。当たり前のような日常が貴重。そんな風景を車内から眺められるスピードで進む世田谷線に乗って、この店に向う。松陰神社前の駅を降りてすぐ、小さな階段を上る。すると温かでラブラブなご夫婦が待っている。
山本幸久のデビュー作『笑う招き猫』2作目の『はなうた日和』は世田谷線沿線の街が舞台。2両だけの電車が軒先を掠めるように走る街々。この2作を読みながら、この店のすぐ下を通る電車を思い浮かべていた。のんびりと、ゆっくりと、温かな世田谷線。線路のすぐ横にはつくしが顔を出し、紫陽花などの花が咲く。母親に抱かれながら、じっと目を輝かせて電車を見入る幼子がいる。当たり前のような日常が貴重。そんな風景を車内から眺められるスピードで進む世田谷線に乗って、この店に向う。松陰神社前の駅を降りてすぐ、小さな階段を上る。すると温かでラブラブなご夫婦が待っている。
「いやぁ、良い肉の日でした!」「とっても美味しい肉の日でしたぁ♡」肉好きの2人が声を揃える。微笑ましいくらいに。ここにも温かでラブラブな2人。山本幸久の2作品に「世田谷線の歌」が掲載されている。もちろん山本幸久オリジナル。♬世田谷線はね(中略)おんなじところ走っていたいの おなじ町見ていたいの でね今日もシモタカとサンチャ行ったり来たり♬ 詳しくは集英社文庫を!












