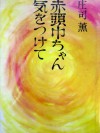中央線沿線には独特の匂いがある。駅毎に個性がありつつ、共通する文化がある。中央線に乗ると、70年代のヒッピー文化の尻尾を引きずっている人がいたり、パンクな方々、いかにもエコロジ〜な人々、インド文化傾倒者などをお見かけする。実に個性的な中央線の人々。一方、中野には「まんだらけ」をはじめとしたサブカルチャーの一大拠点「中野ブロードウェー」があり、七夕まつりで有名な阿佐ヶ谷はジャズの街でもある。荻窪は春木屋をはじめとした東京ラーメンの有名店が集まる街だし、西荻窪は今や骨董店のメッカとなり、住みたい街NO.1の吉祥寺はライブハウスや個性豊かな飲食店が集まる若者の街。そして、高円寺は阿波踊りとロックと古着屋と『純情商店街』…。街のキャラクターも実に多彩である。
中央線沿線には独特の匂いがある。駅毎に個性がありつつ、共通する文化がある。中央線に乗ると、70年代のヒッピー文化の尻尾を引きずっている人がいたり、パンクな方々、いかにもエコロジ〜な人々、インド文化傾倒者などをお見かけする。実に個性的な中央線の人々。一方、中野には「まんだらけ」をはじめとしたサブカルチャーの一大拠点「中野ブロードウェー」があり、七夕まつりで有名な阿佐ヶ谷はジャズの街でもある。荻窪は春木屋をはじめとした東京ラーメンの有名店が集まる街だし、西荻窪は今や骨董店のメッカとなり、住みたい街NO.1の吉祥寺はライブハウスや個性豊かな飲食店が集まる若者の街。そして、高円寺は阿波踊りとロックと古着屋と『純情商店街』…。街のキャラクターも実に多彩である。

 3年程前、その高円寺に新しい“文化”の拠点ができた。その名も「座・高円寺」という演劇が中心の劇場。正式名称は杉並区立杉並芸術会館。阿波踊りホールという常設の練習場まであるのが高円寺らしい。芸術監督に佐藤信、開館時の館長に2011年に逝去された斎藤憐という自由劇場の設立メンバーでもある2人の大御所を据え、運営はアート系のNPOという柔軟さ。この劇場がなかなか良い感じ。演目が年に数回、お気楽夫婦の琴線に触れる。ということで、普段は余り縁のない高円寺の街に出かけることになる。その日も2人のお気に入りのわかぎえふが脚本、演出を手がけた『ワンダー・ガーデン』という芝居を観て、その満足の内容にご機嫌で高円寺の街をふらふらり。
3年程前、その高円寺に新しい“文化”の拠点ができた。その名も「座・高円寺」という演劇が中心の劇場。正式名称は杉並区立杉並芸術会館。阿波踊りホールという常設の練習場まであるのが高円寺らしい。芸術監督に佐藤信、開館時の館長に2011年に逝去された斎藤憐という自由劇場の設立メンバーでもある2人の大御所を据え、運営はアート系のNPOという柔軟さ。この劇場がなかなか良い感じ。演目が年に数回、お気楽夫婦の琴線に触れる。ということで、普段は余り縁のない高円寺の街に出かけることになる。その日も2人のお気に入りのわかぎえふが脚本、演出を手がけた『ワンダー・ガーデン』という芝居を観て、その満足の内容にご機嫌で高円寺の街をふらふらり。

 「やっぱり抱瓶かねぇ〜」妻の提案。慣れない街で、安心して美味しいモノを食べようとすると、自ずと定番の店になる。ということで、結局お気に入りの沖縄料理の抱瓶に向かう。沖縄料理好きのお気楽夫婦、主だった街ごとにお気に入りの店がある。シモキタだったら「Aサインバー」、下高井戸の「ナンクルナイサ」、自由が丘は「なんた浜」、そして高円寺は老舗の「抱瓶」だ。いかにもウチナーの面構えの店の前でにんまり。店に入ると相変わらずの大賑わい。幸い入口すぐのカウンタ席が空いていた。さっそくキンキンに冷えたオリオンの生!そしてA&W(エンダー)メニューで有名なカーリーフライ。(カーリーヘアのようなポテトフライ)これが、身体に悪そうで、旨い。この手のジャンクフードは身体に悪そうなモノほど旨い。
「やっぱり抱瓶かねぇ〜」妻の提案。慣れない街で、安心して美味しいモノを食べようとすると、自ずと定番の店になる。ということで、結局お気に入りの沖縄料理の抱瓶に向かう。沖縄料理好きのお気楽夫婦、主だった街ごとにお気に入りの店がある。シモキタだったら「Aサインバー」、下高井戸の「ナンクルナイサ」、自由が丘は「なんた浜」、そして高円寺は老舗の「抱瓶」だ。いかにもウチナーの面構えの店の前でにんまり。店に入ると相変わらずの大賑わい。幸い入口すぐのカウンタ席が空いていた。さっそくキンキンに冷えたオリオンの生!そしてA&W(エンダー)メニューで有名なカーリーフライ。(カーリーヘアのようなポテトフライ)これが、身体に悪そうで、旨い。この手のジャンクフードは身体に悪そうなモノほど旨い。

 さらに、ミミガーの酢味噌和え。コリコリしたミミガーと酢味噌のバランスがシンプルながら旨い。スンシー(メンマ)イリチーの美味しさときたら、身震いするほどの幸せ。私の大好物。三枚肉と一緒に炒め煮にしたメンマ。豚の脂の甘さがメンマに浸みてこれまた旨い。これがビールに良く合うのだ。そして定番のゴーヤチャンプルー。さっと炒めたゴーヤの苦みと卵の甘さ、熱々のチャンプルーの上で踊る削り節。極上のB級、お気楽な美味。おもわず微笑み、泡盛のロックをオーダー。辛いもの好きの妻は「コーレーグースーください!」と声を上げ、すかさずたっぷり振りかける。「やっぱりウチナーは良いなぁ♫」はふはふと頬張りながら、しみじみと呟く。シメは沖縄すばではなく、ゆしどうふ。さっぱりと美味しい。
さらに、ミミガーの酢味噌和え。コリコリしたミミガーと酢味噌のバランスがシンプルながら旨い。スンシー(メンマ)イリチーの美味しさときたら、身震いするほどの幸せ。私の大好物。三枚肉と一緒に炒め煮にしたメンマ。豚の脂の甘さがメンマに浸みてこれまた旨い。これがビールに良く合うのだ。そして定番のゴーヤチャンプルー。さっと炒めたゴーヤの苦みと卵の甘さ、熱々のチャンプルーの上で踊る削り節。極上のB級、お気楽な美味。おもわず微笑み、泡盛のロックをオーダー。辛いもの好きの妻は「コーレーグースーください!」と声を上げ、すかさずたっぷり振りかける。「やっぱりウチナーは良いなぁ♫」はふはふと頬張りながら、しみじみと呟く。シメは沖縄すばではなく、ゆしどうふ。さっぱりと美味しい。
「中華料理も良いけど、沖縄料理もしみじみと良いよねぇ」と妻。芝居と食事の満足感と満腹感に身を包み、高円寺の街をふらふらと。工事中のバルーンがお見送り。高円寺の顔とも言える店で、街の魅力を味わった。
■食いしん坊夫婦の御用達 「抱瓶」 お店の基本情報、過去の訪問記
 ある日、ばったりと前職の後輩に遇った。小田急線の経堂駅、昨年完成したばかりの駅ビル。彼は部下を連れて自社施設を視察中。ということで、もちろん彼らは仕事中。私はと言えば、ノーギャラの仕事である地元の「街づくり」のために、経堂の街をぶらぶらと事例研究の散歩中。仕事中なのか、街をぶらぶらに重きがあるのか、我ながらビミョー。そして名刺交換。ふむふむ、自社ポイント系のお仕事なのか、それは今後は関わりがありそうだねと立ち話をした後で、その場は別れた。私は知人にばったりと遭うことが得意だ。街を歩いていると思わぬところで知り合いに出くわす。多い時には、日に何度も。とは言え、それ以降に縁がある場合も、それっきりの場合もある。小田急氏の場合は、縁があった。それからしばらく経ったある日、彼からメールが届いた。仕事で絡みがありそうだ。さっそく飲みの約束をする。場所は、偶然出会った経堂の街。
ある日、ばったりと前職の後輩に遇った。小田急線の経堂駅、昨年完成したばかりの駅ビル。彼は部下を連れて自社施設を視察中。ということで、もちろん彼らは仕事中。私はと言えば、ノーギャラの仕事である地元の「街づくり」のために、経堂の街をぶらぶらと事例研究の散歩中。仕事中なのか、街をぶらぶらに重きがあるのか、我ながらビミョー。そして名刺交換。ふむふむ、自社ポイント系のお仕事なのか、それは今後は関わりがありそうだねと立ち話をした後で、その場は別れた。私は知人にばったりと遭うことが得意だ。街を歩いていると思わぬところで知り合いに出くわす。多い時には、日に何度も。とは言え、それ以降に縁がある場合も、それっきりの場合もある。小田急氏の場合は、縁があった。それからしばらく経ったある日、彼からメールが届いた。仕事で絡みがありそうだ。さっそく飲みの約束をする。場所は、偶然出会った経堂の街。
 小田急氏を知る妻を一緒にと誘うと、経堂だったら行きたい店があるという。「蜀彩(しょくさい)」という四川料理の店らしい。さっそく予約して訪問。店は小田急線の経堂駅から数分。農大通り沿いにある小さな看板を目印に階段を上る。ドアを開けるとこぢんまりとした店は先客の活気で溢れ、ほぼ満席。遅れると連絡があった妻を待ちながら、仕事の話は済ませておこうと話し込む。しばらくして妻が到着。嬉々としてメニューを眺め、いくつかチョイス。夫妻肺片(ハチノス、牛タン、牛スネの辛味ソース和え)、雲白肉(ゆで豚肉の特製辛味にんにくソース)などをオーダー。出て来た料理はいかにも辛そうな面構え。怯えながらもひと口。んんんっ旨いっ!ラー油や唐辛子の辣(ラー:辛味)、花椒の麻味(マーウェイ)という痺れる辛さ、食材の鮮(シェン)旨さが一気に口の中に溢れる。辛さだけではなく、肉の旨味に甘みさえ感じる。これは素晴らしい。
小田急氏を知る妻を一緒にと誘うと、経堂だったら行きたい店があるという。「蜀彩(しょくさい)」という四川料理の店らしい。さっそく予約して訪問。店は小田急線の経堂駅から数分。農大通り沿いにある小さな看板を目印に階段を上る。ドアを開けるとこぢんまりとした店は先客の活気で溢れ、ほぼ満席。遅れると連絡があった妻を待ちながら、仕事の話は済ませておこうと話し込む。しばらくして妻が到着。嬉々としてメニューを眺め、いくつかチョイス。夫妻肺片(ハチノス、牛タン、牛スネの辛味ソース和え)、雲白肉(ゆで豚肉の特製辛味にんにくソース)などをオーダー。出て来た料理はいかにも辛そうな面構え。怯えながらもひと口。んんんっ旨いっ!ラー油や唐辛子の辣(ラー:辛味)、花椒の麻味(マーウェイ)という痺れる辛さ、食材の鮮(シェン)旨さが一気に口の中に溢れる。辛さだけではなく、肉の旨味に甘みさえ感じる。これは素晴らしい。
 美味しい店の料理には中毒性がある。相性が良いと感じた店には、すぐにまた来なくちゃ!と思わせる引力がある。蜀彩はまさしくそんな店だった。蜀彩の辛旨の深い味わいは、舌と脳中枢に刻み込まれた。舌に辛旨の後味がからみつく。美味の記憶が断続的に蘇る。いかんっ!どうしてもまた食べたい。我慢できんっ!小田急氏と訪問した2日後、スカッシュ仲間を誘い3人で再訪した。前回の訪問で気になりながらも食べられなかったメニューを中心に、店の看板メニューらしい口水鶏(よだれ鶏)、四川の王道として押さえておきたい麻婆豆腐などをセレクト。まずは、よだれ鶏。くはぁ〜っと辛旨い。名前の通り、口の中に旨味とともに涎が溢れる。多くの香辛料で複雑に辛く香りの良いソースの中にピーナッツ、胡麻、サツマイモ…えっ?芋?これがまた絶妙なハーモニー。インパクトある旨さ。クセになる辛さ。
美味しい店の料理には中毒性がある。相性が良いと感じた店には、すぐにまた来なくちゃ!と思わせる引力がある。蜀彩はまさしくそんな店だった。蜀彩の辛旨の深い味わいは、舌と脳中枢に刻み込まれた。舌に辛旨の後味がからみつく。美味の記憶が断続的に蘇る。いかんっ!どうしてもまた食べたい。我慢できんっ!小田急氏と訪問した2日後、スカッシュ仲間を誘い3人で再訪した。前回の訪問で気になりながらも食べられなかったメニューを中心に、店の看板メニューらしい口水鶏(よだれ鶏)、四川の王道として押さえておきたい麻婆豆腐などをセレクト。まずは、よだれ鶏。くはぁ〜っと辛旨い。名前の通り、口の中に旨味とともに涎が溢れる。多くの香辛料で複雑に辛く香りの良いソースの中にピーナッツ、胡麻、サツマイモ…えっ?芋?これがまた絶妙なハーモニー。インパクトある旨さ。クセになる辛さ。
 そしてこの店、四川の辛い料理だけではなく、豆苗炒め、卵とトマト炒め、白レバーの赤酒漬けなどの脇役?もレベルが高い。「前の時もそうだったんだけど、料理が出てくるの速いのよね」「そうなんですよね、私もそう思ってました」と妻と友人も納得。確かに、2回転目の席もある程の賑わいにも関わらず、実に良いテンポで料理が出て来るのだ。これも好印象。シェフ自らもフロアに出て来るサービスはまだ固さが残るけれど、これは間違いなく良い店だ。頻繁に訪れたくなる店だ。デザートの盛り合わせまで食べ切った3人、満足感を身体一杯に詰め込んで街を歩く。友人と別れた後、駅前の大型スーパーへ。小田急電鉄が操作場などの広大な土地を持っていたからこその再開発ではあるものの、経堂駅前周辺の商業施設などの充実ぶりは素晴らしい。画一的な大資本のテナントが目立つけれど、街が賑わえば新たな出店もある。街に彩りが加わる。繁盛店が増えれば街も賑わう。街と店がそれぞれ魅力を持ち、人を引きつける引力を持つ好循環。
そしてこの店、四川の辛い料理だけではなく、豆苗炒め、卵とトマト炒め、白レバーの赤酒漬けなどの脇役?もレベルが高い。「前の時もそうだったんだけど、料理が出てくるの速いのよね」「そうなんですよね、私もそう思ってました」と妻と友人も納得。確かに、2回転目の席もある程の賑わいにも関わらず、実に良いテンポで料理が出て来るのだ。これも好印象。シェフ自らもフロアに出て来るサービスはまだ固さが残るけれど、これは間違いなく良い店だ。頻繁に訪れたくなる店だ。デザートの盛り合わせまで食べ切った3人、満足感を身体一杯に詰め込んで街を歩く。友人と別れた後、駅前の大型スーパーへ。小田急電鉄が操作場などの広大な土地を持っていたからこその再開発ではあるものの、経堂駅前周辺の商業施設などの充実ぶりは素晴らしい。画一的な大資本のテナントが目立つけれど、街が賑わえば新たな出店もある。街に彩りが加わる。繁盛店が増えれば街も賑わう。街と店がそれぞれ魅力を持ち、人を引きつける引力を持つ好循環。
「経堂に引っ越す?スポーツクラブもあるし、パクチーハウスもあるし…」ちょっと待って、ウチの街も頑張ってるし、10年も経てば京王線も立体化されて、踏切がなくなってね…。「10年かぁ〜」いささか不満そうな妻。う〜む、確かに魅力的な街ではある。けれど、負けるな!地元の町づくり!ってことで(苦笑)。
■食いしん坊夫婦の御用達 「中国四川料理 蜀彩」 *お店のデータなどを掲載

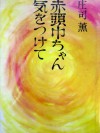 買った本が捨てられない。正確には、自分で買った本を処分できない。もっと正確に言えば、手に入れて気に入って読んだ本を手放すことができない。「本棚に入らないから捨てようよ!」といつもブツブツ言う妻に明確に答えられない、その捨てられない理由は何だろう。再度読み返そうと思った時にすぐに手に取れるということもある。読んだ時のことを背表紙を眺めながら思い出すのが好きということもある。老後にゆったりと読み返したいと思っているから、というのは言い訳に違いない。今も新刊が増え、全部を読み返すにはずいぶんと長生きをしなければならないだろうし。けれども稀なケースとして、実際に読み直してまた楽しむことがある。そして読み返してもなお色褪せないどころか、今でも輝き続けている、あるいは新たな輝きを持つ物語がある。私にとっては『赤頭巾ちゃん気をつけて』が、まさしくそんな作品だ。
買った本が捨てられない。正確には、自分で買った本を処分できない。もっと正確に言えば、手に入れて気に入って読んだ本を手放すことができない。「本棚に入らないから捨てようよ!」といつもブツブツ言う妻に明確に答えられない、その捨てられない理由は何だろう。再度読み返そうと思った時にすぐに手に取れるということもある。読んだ時のことを背表紙を眺めながら思い出すのが好きということもある。老後にゆったりと読み返したいと思っているから、というのは言い訳に違いない。今も新刊が増え、全部を読み返すにはずいぶんと長生きをしなければならないだろうし。けれども稀なケースとして、実際に読み直してまた楽しむことがある。そして読み返してもなお色褪せないどころか、今でも輝き続けている、あるいは新たな輝きを持つ物語がある。私にとっては『赤頭巾ちゃん気をつけて』が、まさしくそんな作品だ。
作者は庄司薫。主人公の名前も同じ「庄司薫」という18歳の高校3年生。『赤頭巾ちゃん〜』に続く『さよなら怪傑黒頭巾』『白鳥の歌なんか聞こえない』『ぼくの大好きな青髯』を合わせた4連作の第1作め。それぞれの作品に冠された4色は、古代中国の五行思想における赤(朱雀)、黒(玄武)、白(白虎)、青(青龍)。それぞれ南北西東、人生の夏冬秋春を意味する物語。作者によれば「みんなを幸福にするためにはどうすればいいか」という問いを抱えて、世界の四方に出かけて、何かを予感して封印する輪廻転生の物語。高校時代に初めて読んだこの4冊は私にとって憧れの世界だった。友人たちとの会話、主人公の語り口、軽やかでオシャレでちょっとキザなレトリック。柔らかでしなやかな知性に溢れ、それでいて若さのまっただ中でもがく、ナイーブな高校生。男の子、いかに生きるべきかなどと呟きながら。本棚の隅に妻の追求から逃れるように『赤頭巾ちゃん〜』たちが収まっている。その奥付によると初版は昭和44年8月10日、私の持っているのが昭和48年11月10日の、なんと47版!そう、当時の表現で言えば、猛烈に(笑)売れていた小説なのだ。
 そして、2012年。4部作が改めて文庫化される。3月から毎月1冊づつ、「新潮文庫」から出版されるという。福田彰二という本名で受賞した『喪失』が中央公論新人賞を受賞したことから、今までは文庫も含めた全ての庄司薫の著作のほとんどは中央公論社が版元だった。どんな経緯があったかは知らないけれど、3月に出たばかりの『赤頭巾ちゃん気をつけて』新潮文庫版を手に取った。巻末には「あわや半世紀のあとがき」というわずか2Pだけの文章。どうやら庄司薫本人が書いた(当然だけれど)ようだ。そのあとがきを読むために迷わず購入。何しろ、4つの物語を書き終えた後、本人が言うところの「総退却」してしまった作者はほとんど表舞台に出てこない。新たな文章にお目にかかれない。ちなみに、奥さまでピアニストの中村紘子さんの収入で暮している訳ではなく、不動産等の資産運用で悠々自適の、まさしく憧れの生活をなさっているようだ。
そして、2012年。4部作が改めて文庫化される。3月から毎月1冊づつ、「新潮文庫」から出版されるという。福田彰二という本名で受賞した『喪失』が中央公論新人賞を受賞したことから、今までは文庫も含めた全ての庄司薫の著作のほとんどは中央公論社が版元だった。どんな経緯があったかは知らないけれど、3月に出たばかりの『赤頭巾ちゃん気をつけて』新潮文庫版を手に取った。巻末には「あわや半世紀のあとがき」というわずか2Pだけの文章。どうやら庄司薫本人が書いた(当然だけれど)ようだ。そのあとがきを読むために迷わず購入。何しろ、4つの物語を書き終えた後、本人が言うところの「総退却」してしまった作者はほとんど表舞台に出てこない。新たな文章にお目にかかれない。ちなみに、奥さまでピアニストの中村紘子さんの収入で暮している訳ではなく、不動産等の資産運用で悠々自適の、まさしく憧れの生活をなさっているようだ。
そして再読。舞台は1969年の東京。春。主人公の薫は、学校群制度が導入される直前の、東大に毎年200名近く入学していた日比谷高校の3年生。東大入試が中止となり、大学に行くことを止めることを幼なじみの由美ちゃんに伝えようとした朝から、ふんだりけったりの展開の後、銀座の旭屋書店の前でカナリア色のコートを着た小さな女の子に爪を剥がしたての足を思いっきり踏まれ、そして彼女が買おうと慌てていた『赤ずきんちゃん』を一緒に選んであげる。そして、それまでの自分の抱えたトゲトゲを全て許せる気持になって、その日の夜に由美ちゃんと仲直り、というそれだけの、たった半日の物語。けれど、半世紀近く経った今でも、その文章は変わらず瑞々しく、物語は古びることなく、若くはなくなった私に柔らかく響いて来る。書出しの文章をほぼ覚えていることに驚く。それどころか、読み返して、当時は理解できなかった小さなエピソードに気付く。物語の輪郭や陰影がはっきりとする。当時は未知の街だった舞台、東京を辿ることができる。新たな楽しみ方を発見する。40年以上前に読んだ時と変わったのは自分だけなんだと気付く。
「そうまで言うなら、読んでみるかぁ」と、庄司薫作品は未読の妻。未読の方にもおススメしたい。まして村上春樹がお好きなら。なぜなら、村上春樹が80年代に新たな日本の小説の地平を拓いたように、70年代は庄司薫だったんだ。…と庄司薫風におススメしてみようと思った訳だ。再読の方も、ぜひ。

 中央線沿線には独特の匂いがある。駅毎に個性がありつつ、共通する文化がある。中央線に乗ると、70年代のヒッピー文化の尻尾を引きずっている人がいたり、パンクな方々、いかにもエコロジ〜な人々、インド文化傾倒者などをお見かけする。実に個性的な中央線の人々。一方、中野には「まんだらけ」をはじめとしたサブカルチャーの一大拠点「中野ブロードウェー」があり、七夕まつりで有名な阿佐ヶ谷はジャズの街でもある。荻窪は春木屋をはじめとした東京ラーメンの有名店が集まる街だし、西荻窪は今や骨董店のメッカとなり、住みたい街NO.1の吉祥寺はライブハウスや個性豊かな飲食店が集まる若者の街。そして、高円寺は阿波踊りとロックと古着屋と『純情商店街』…。街のキャラクターも実に多彩である。
中央線沿線には独特の匂いがある。駅毎に個性がありつつ、共通する文化がある。中央線に乗ると、70年代のヒッピー文化の尻尾を引きずっている人がいたり、パンクな方々、いかにもエコロジ〜な人々、インド文化傾倒者などをお見かけする。実に個性的な中央線の人々。一方、中野には「まんだらけ」をはじめとしたサブカルチャーの一大拠点「中野ブロードウェー」があり、七夕まつりで有名な阿佐ヶ谷はジャズの街でもある。荻窪は春木屋をはじめとした東京ラーメンの有名店が集まる街だし、西荻窪は今や骨董店のメッカとなり、住みたい街NO.1の吉祥寺はライブハウスや個性豊かな飲食店が集まる若者の街。そして、高円寺は阿波踊りとロックと古着屋と『純情商店街』…。街のキャラクターも実に多彩である。
 3年程前、その高円寺に新しい“文化”の拠点ができた。その名も「座・高円寺」という演劇が中心の劇場。正式名称は杉並区立杉並芸術会館。阿波踊りホールという常設の練習場まであるのが高円寺らしい。芸術監督に佐藤信、開館時の館長に2011年に逝去された斎藤憐という自由劇場の設立メンバーでもある2人の大御所を据え、運営はアート系のNPOという柔軟さ。この劇場がなかなか良い感じ。演目が年に数回、お気楽夫婦の琴線に触れる。ということで、普段は余り縁のない高円寺の街に出かけることになる。その日も2人のお気に入りのわかぎえふが脚本、演出を手がけた『ワンダー・ガーデン』という芝居を観て、その満足の内容にご機嫌で高円寺の街をふらふらり。
3年程前、その高円寺に新しい“文化”の拠点ができた。その名も「座・高円寺」という演劇が中心の劇場。正式名称は杉並区立杉並芸術会館。阿波踊りホールという常設の練習場まであるのが高円寺らしい。芸術監督に佐藤信、開館時の館長に2011年に逝去された斎藤憐という自由劇場の設立メンバーでもある2人の大御所を据え、運営はアート系のNPOという柔軟さ。この劇場がなかなか良い感じ。演目が年に数回、お気楽夫婦の琴線に触れる。ということで、普段は余り縁のない高円寺の街に出かけることになる。その日も2人のお気に入りのわかぎえふが脚本、演出を手がけた『ワンダー・ガーデン』という芝居を観て、その満足の内容にご機嫌で高円寺の街をふらふらり。
 「やっぱり抱瓶かねぇ〜」妻の提案。慣れない街で、安心して美味しいモノを食べようとすると、自ずと定番の店になる。ということで、結局お気に入りの沖縄料理の抱瓶に向かう。沖縄料理好きのお気楽夫婦、主だった街ごとにお気に入りの店がある。シモキタだったら「Aサインバー」、下高井戸の「ナンクルナイサ」、自由が丘は「なんた浜」、そして高円寺は老舗の「抱瓶」だ。いかにもウチナーの面構えの店の前でにんまり。店に入ると相変わらずの大賑わい。幸い入口すぐのカウンタ席が空いていた。さっそくキンキンに冷えたオリオンの生!そしてA&W(エンダー)メニューで有名なカーリーフライ。(カーリーヘアのようなポテトフライ)これが、身体に悪そうで、旨い。この手のジャンクフードは身体に悪そうなモノほど旨い。
「やっぱり抱瓶かねぇ〜」妻の提案。慣れない街で、安心して美味しいモノを食べようとすると、自ずと定番の店になる。ということで、結局お気に入りの沖縄料理の抱瓶に向かう。沖縄料理好きのお気楽夫婦、主だった街ごとにお気に入りの店がある。シモキタだったら「Aサインバー」、下高井戸の「ナンクルナイサ」、自由が丘は「なんた浜」、そして高円寺は老舗の「抱瓶」だ。いかにもウチナーの面構えの店の前でにんまり。店に入ると相変わらずの大賑わい。幸い入口すぐのカウンタ席が空いていた。さっそくキンキンに冷えたオリオンの生!そしてA&W(エンダー)メニューで有名なカーリーフライ。(カーリーヘアのようなポテトフライ)これが、身体に悪そうで、旨い。この手のジャンクフードは身体に悪そうなモノほど旨い。
 さらに、ミミガーの酢味噌和え。コリコリしたミミガーと酢味噌のバランスがシンプルながら旨い。スンシー(メンマ)イリチーの美味しさときたら、身震いするほどの幸せ。私の大好物。三枚肉と一緒に炒め煮にしたメンマ。豚の脂の甘さがメンマに浸みてこれまた旨い。これがビールに良く合うのだ。そして定番のゴーヤチャンプルー。さっと炒めたゴーヤの苦みと卵の甘さ、熱々のチャンプルーの上で踊る削り節。極上のB級、お気楽な美味。おもわず微笑み、泡盛のロックをオーダー。辛いもの好きの妻は「コーレーグースーください!」と声を上げ、すかさずたっぷり振りかける。「やっぱりウチナーは良いなぁ♫」はふはふと頬張りながら、しみじみと呟く。シメは沖縄すばではなく、ゆしどうふ。さっぱりと美味しい。
さらに、ミミガーの酢味噌和え。コリコリしたミミガーと酢味噌のバランスがシンプルながら旨い。スンシー(メンマ)イリチーの美味しさときたら、身震いするほどの幸せ。私の大好物。三枚肉と一緒に炒め煮にしたメンマ。豚の脂の甘さがメンマに浸みてこれまた旨い。これがビールに良く合うのだ。そして定番のゴーヤチャンプルー。さっと炒めたゴーヤの苦みと卵の甘さ、熱々のチャンプルーの上で踊る削り節。極上のB級、お気楽な美味。おもわず微笑み、泡盛のロックをオーダー。辛いもの好きの妻は「コーレーグースーください!」と声を上げ、すかさずたっぷり振りかける。「やっぱりウチナーは良いなぁ♫」はふはふと頬張りながら、しみじみと呟く。シメは沖縄すばではなく、ゆしどうふ。さっぱりと美味しい。