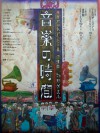2011年3月11日14時46分、多くのものが破壊された。けれど、生まれたものがある。そして、打破しなければいけないものもある。
 お気楽夫婦が住むマンションは、世田谷の外れの街の駅近くにある100戸弱の規模。2基あるエレベータで住民同士が乗り合わせても、挨拶をするのは半数程度。それも元気に声に出して挨拶する子供たち以外は、むにゃむにゃと口の中でことばにならない声を出したり、軽く会釈する人がほとんど。けれど不思議なことに、管理室や掃除のおじちゃんには誰もが「おはようございます」ときちんと挨拶し、出かけて行く。決して住民に社会性や交流能力が欠如している訳ではない。住民同士の多くは顔見知りでもないし、集会室がある訳でもなく、管理組合の総会があっても参加するのは20人程度。2〜300人の住民が最小限の交流で同じ建物の中に暮らしている。こうして書きながら、同じマンションに住んでいる人数も知らないという事実に気付く、典型的な都市型集合住宅。
お気楽夫婦が住むマンションは、世田谷の外れの街の駅近くにある100戸弱の規模。2基あるエレベータで住民同士が乗り合わせても、挨拶をするのは半数程度。それも元気に声に出して挨拶する子供たち以外は、むにゃむにゃと口の中でことばにならない声を出したり、軽く会釈する人がほとんど。けれど不思議なことに、管理室や掃除のおじちゃんには誰もが「おはようございます」ときちんと挨拶し、出かけて行く。決して住民に社会性や交流能力が欠如している訳ではない。住民同士の多くは顔見知りでもないし、集会室がある訳でもなく、管理組合の総会があっても参加するのは20人程度。2〜300人の住民が最小限の交流で同じ建物の中に暮らしている。こうして書きながら、同じマンションに住んでいる人数も知らないという事実に気付く、典型的な都市型集合住宅。
その日の夜、勤務先から2時間半かけて歩いて帰ってきた妻。お互いにほっとして、どこかに行ってしまっていた空腹を思い出す。深夜の食事に出かけようと外に出た。エレベータ前には普段見かけない同じフロアに住む(であろう)若い女性。いつもなら、おそらく互いに曖昧に会釈する程度。ところが、「ガス止まってませんか」と声を掛けられる。えぇ、大丈夫です。リセットボタンを押して戻さないと回復しないんですよね。ウチも止まっていたんで、さっきやりました。ぎこちないながらも短い会話が続く。戸惑いながらも、ぽっと小さな温かいものが生まれた。
翌日、同じフロアに独りで住む(らしい)お婆ちゃんの部屋を知人が訪ねている場に出会った。玄関先で会話している横を通り過ぎようとすると、「いかがですか。大丈夫でしたか」とお婆ちゃんに声を掛けられる。はい、凄かったですねと返した後で、そちらはいかがでしたかと気遣うことばが返せなかったことに密かに赤面する。けれど、お婆ちゃんの柔らかな笑顔を思い出し、自己嫌悪の刺もすぐに抜け、小さく繋がったコミュニティを実感する。元々あったコミュニティの土壌から、小さな芽が出るきっかけが生まれた。
…日本中で、きっとこんなことが起きている♡
mixiやFacebookなどのSNSを通じて伝えられるエピソードがある。マスメディアで伝えられる美談がある。避難所で率先して救援物資を届ける中学生たちが、元気な自分たちが食べ物と一緒に元気も届けたいとコメントする。非常時にも関わらず、普段通りにホームにきちんと列を作って並ぶ人たちの画像が紹介される。被災地で給水の列に並ぶ人々、都心の駅で改札に並ぶ人々。非常時だからこそ、整然と、混乱なく、自主的に行列が生まれる。日本人の冷静さ、社会性の高さ、互助の精神を讃える海外からの声が紹介される。それを誇りに思うとの書き込みがある。共感が、誇りが、そして(場合によってはややいびつな)愛国心が生まれる。
一方で、不用意なチェーンメールが生まれる。デマが流れる。メールで、ツイッターで、SNSを通じて、口伝よりも圧倒的に速いスピードで拡散する。ソーシャルネットワークは個々のつながりで閉じられていながら、同時に不特定多数に開いている。会ったこともない人同士がネットワークで結びつき、(発信源の悪意を除けば)善意と信じる情報が津波のように伝わって行く。時には革命さえ生んでしまうエネルギーでもあるけれど、幸い日本では情報伝達による悲劇は生まれていない。
*ラジオ放送さえ普及していなかった1923年の関東大震災。その際に起きたデマの流布によって悲劇が起きた。閉じたコミュニティの結びつきが強かった時代の惨事でもある。
「今度の週末、東京を脱出して、いっそ浜松に帰ろうか」震災後、従業員間の非常時伝達ルートの再整備を行っているという妻が、珍しくネガティブ発言。彼女は子供の頃から徹底した地震対策の教育を受ける静岡県出身。節電に努め、非常用にとバスタブの水を流さず、災害用の持ち出しグッズの点検を怠らない。けれど、発生後から延々と流れ続ける被災地や原発の報道、毎日続く余震などから来る息苦しさ、閉塞感からは逃れられない。震災発生翌日に予定していた友人たちとの旅行も中止にした。震災前、連休に検討していた帰省に関しても迷っていた。
東京を離れるっていうのは、敵前逃亡のような気がして嫌だなぁ。妻にそう告げた。ホントの敵はまだ来てないんだろうし、今は東京を離れたくない。浜松に行くのは刀折れ矢尽きてからで良いんじゃない。そこに静岡県東部を震源とする地震。
「ん。いずれにしても行ってる場合じゃないね」妻は気持の切換えが実に速い。「まず、やれることをやるってことだね」そう。閉塞感を打破することは、逃げることではない。「本城さんに食べに行くのは予定通りで良いよね。いつも通り、フツーに消費するところはお金をきちんと使わないと!」そう、それこそお気楽夫婦の本領。必要以上に(この匙加減が難しいのだけれど)不謹慎だと自粛したり、買溜めは論外としても消費や行動に気遣うことはない。誰かが消費してはじめて経済は回り、間接的に被災地に支援ができる。もちろん直接的な支援も。ニュージーランドに続き、ネットから義援金を送る手はずを整える妻。…そして、そんな時でもクレジットカードを使い、ポイントを貯めようとするところがお気楽妻の本領。
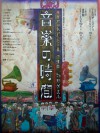 中島らも。作家で、役者で、ミュージシャン。そして、ジャンキー。2004年没、享年52歳。中島が観に行った芝居が余りにつまらなくて立ち上げた劇団が、笑殺軍団リリパットアーミー。現在は、座長であり脚本家、役者のわかぎゑふがリリパットアーミーⅡを率いる。お気楽夫婦が初めてその舞台を観たのは1997年。劇団の中心は中島らもからわかぎに移っており、中島らもは平劇団員として客演の役者のように舞台に上がっているだけだった。はじめは大阪の笑いにとまどいながらも、夫婦揃ってすっかり嵌り、わかぎが主宰するもうひとつの劇団ラックシステムも含め、毎回欠かさず観に行っている。リリパ設立から25年、関西を中心とした人気劇団ではあるけれど、公演はいずれも小さな劇場。必ずしも商業的に成功しているとは言えない。
中島らも。作家で、役者で、ミュージシャン。そして、ジャンキー。2004年没、享年52歳。中島が観に行った芝居が余りにつまらなくて立ち上げた劇団が、笑殺軍団リリパットアーミー。現在は、座長であり脚本家、役者のわかぎゑふがリリパットアーミーⅡを率いる。お気楽夫婦が初めてその舞台を観たのは1997年。劇団の中心は中島らもからわかぎに移っており、中島らもは平劇団員として客演の役者のように舞台に上がっているだけだった。はじめは大阪の笑いにとまどいながらも、夫婦揃ってすっかり嵌り、わかぎが主宰するもうひとつの劇団ラックシステムも含め、毎回欠かさず観に行っている。リリパ設立から25年、関西を中心とした人気劇団ではあるけれど、公演はいずれも小さな劇場。必ずしも商業的に成功しているとは言えない。
 昨夜(ある週末と普段なら書くところ、今回は敢えて昨夜という)いつものようにご近所の友人夫妻を誘い、下北沢のザ・スズナリで初日を迎えた『音楽の時間』を観た。相変わらず良い舞台だった。大阪という街に拘り、丁寧に構成された脚本。2時間という公演時間内に、それぞれの登場人物を巧みに描き、観る者に感情移入させ、芝居の合間にきちんと笑いを織り込んで行く。わかぎの脚本には“こ難しさ”はない。むしろエンタテインメント。関西弁の微妙なニュアンスを大切にしながらも、ことばで遊び、ことばを紡ぐ巧みさは心地良い。そして重くなりがちなテーマを扱う時も、ある場面では大阪の笑いで物語の流れを緩め、ある時は大阪弁でテンポ良く畳掛ける。2時間という時間を全く飽きさせず、笑いに巻き込み、涙を誘い、楽しませる。まさしく(もちろん関東にも通用する)関西小劇場界のエンタテインメント。
昨夜(ある週末と普段なら書くところ、今回は敢えて昨夜という)いつものようにご近所の友人夫妻を誘い、下北沢のザ・スズナリで初日を迎えた『音楽の時間』を観た。相変わらず良い舞台だった。大阪という街に拘り、丁寧に構成された脚本。2時間という公演時間内に、それぞれの登場人物を巧みに描き、観る者に感情移入させ、芝居の合間にきちんと笑いを織り込んで行く。わかぎの脚本には“こ難しさ”はない。むしろエンタテインメント。関西弁の微妙なニュアンスを大切にしながらも、ことばで遊び、ことばを紡ぐ巧みさは心地良い。そして重くなりがちなテーマを扱う時も、ある場面では大阪の笑いで物語の流れを緩め、ある時は大阪弁でテンポ良く畳掛ける。2時間という時間を全く飽きさせず、笑いに巻き込み、涙を誘い、楽しませる。まさしく(もちろん関東にも通用する)関西小劇場界のエンタテインメント。
 贔屓の引き倒しということばがある。素人の書くこんな記事に何の影響力もないのだけれど、(気に入りの芝居は特に)公演中には記事を書かないことにしている。けれど、舞台初日である昨夜、拍手が鳴り止まない舞台の上で、座長の挨拶に続く平日の公演はまだ“売る程チケットがある”というコメントが淋しかった。こんなに小さな小屋なのに、こんなに良い芝居の席が、平日とは言え埋まっていないのが悔しかった。そこで、どんなに小さな影響でも良い、ネタバレしないように注意しながら、公演中に記事を書くことにした。明治のはじめ、日本人が西洋音楽を聴き始めた頃の大阪。海外留学から帰って来た音楽家の卵。偶然知り合った置屋の女たちの大阪弁の会話が音階を持つことに気付く。そして五・七・五の和歌のリズムがメロディに重なり、日本で初めて西洋音楽が生まれる。そんなシーンに鳥肌が立った。
贔屓の引き倒しということばがある。素人の書くこんな記事に何の影響力もないのだけれど、(気に入りの芝居は特に)公演中には記事を書かないことにしている。けれど、舞台初日である昨夜、拍手が鳴り止まない舞台の上で、座長の挨拶に続く平日の公演はまだ“売る程チケットがある”というコメントが淋しかった。こんなに小さな小屋なのに、こんなに良い芝居の席が、平日とは言え埋まっていないのが悔しかった。そこで、どんなに小さな影響でも良い、ネタバレしないように注意しながら、公演中に記事を書くことにした。明治のはじめ、日本人が西洋音楽を聴き始めた頃の大阪。海外留学から帰って来た音楽家の卵。偶然知り合った置屋の女たちの大阪弁の会話が音階を持つことに気付く。そして五・七・五の和歌のリズムがメロディに重なり、日本で初めて西洋音楽が生まれる。そんなシーンに鳥肌が立った。
 「おもしろかったねぇ♬」公演中、隣の席で笑い転げるご近所の友人夫妻の横で、薄〜いリアクションで芝居を観ていた妻が呟く。舞台を観ている様子だけからは決して伺えないけれど、彼女はわかぎの脚本が大好きで、コング桑田や野田晋市(今回は出演せず)などの役者が大のお気に入り。この劇団の芝居だけは必ずパンフレットを購入し、恒例の終演後のサイン会の列に並ぶ。その上、昨夜は舞台での物販案内でコング桑田が言うところの早割ではなく遅割、早い話が売れ残った2011年カレンダーまで購入。手作り感覚満載のカレンダーの3月、コング桑田を眺めてご満悦。劇団員が客演で出演する舞台のチェックも欠かさない妻は、劇団の公式サイト「玉造小劇店」を頻繁に訪問。もちろん劇団のファンクラブ会員にもなり、公演の度に友人夫妻を誘うことも忘れない。
「おもしろかったねぇ♬」公演中、隣の席で笑い転げるご近所の友人夫妻の横で、薄〜いリアクションで芝居を観ていた妻が呟く。舞台を観ている様子だけからは決して伺えないけれど、彼女はわかぎの脚本が大好きで、コング桑田や野田晋市(今回は出演せず)などの役者が大のお気に入り。この劇団の芝居だけは必ずパンフレットを購入し、恒例の終演後のサイン会の列に並ぶ。その上、昨夜は舞台での物販案内でコング桑田が言うところの早割ではなく遅割、早い話が売れ残った2011年カレンダーまで購入。手作り感覚満載のカレンダーの3月、コング桑田を眺めてご満悦。劇団員が客演で出演する舞台のチェックも欠かさない妻は、劇団の公式サイト「玉造小劇店」を頻繁に訪問。もちろん劇団のファンクラブ会員にもなり、公演の度に友人夫妻を誘うことも忘れない。
「やっぱり芝居は楽しくなくっちゃねぇ」と妻。表現は平坦でシンプルだけれど、長年の付き合いで妻の発言の行間を読めば、これは席が埋まっていないという平日にまた観に行こうか!という勢い。ということで、皆さま、どうか劇場へ!
 野田秀樹。役者で、演出家。学生時代に立ち上げた劇団夢の遊眠社を率いて、日本演劇界に新たな風を巻き起こした。初めて野田の芝居を観たのは1987年の『明るい冒険』。もう小劇団と呼べる公演規模ではなく、会場は青山劇場。自動車メーカーまで冠スポンサーに付く人気の劇団だった。上杉祥三、羽場裕一、円城寺あやなどの人気役者も生まれ、小劇場第三世代の…などという能書きは長く書くまい。ダイナミックな脚本、複雑な物語の構成、鳥肌が立ってしまうような演出、独特のセリフとことば遊び、そして何よりも野田の存在感に惹かれ、その舞台を観続けてきた。遊眠社解散後にロンドン留学、帰国後に結成したNODA MAPは、前よりは取り易くなったものの、今もなかなかチケットが買えない人気。お気楽夫婦も毎回トライしながら実際に観に行けたのは6割程度。それでも毎回観に行こうと思わせる魅力がある。
野田秀樹。役者で、演出家。学生時代に立ち上げた劇団夢の遊眠社を率いて、日本演劇界に新たな風を巻き起こした。初めて野田の芝居を観たのは1987年の『明るい冒険』。もう小劇団と呼べる公演規模ではなく、会場は青山劇場。自動車メーカーまで冠スポンサーに付く人気の劇団だった。上杉祥三、羽場裕一、円城寺あやなどの人気役者も生まれ、小劇場第三世代の…などという能書きは長く書くまい。ダイナミックな脚本、複雑な物語の構成、鳥肌が立ってしまうような演出、独特のセリフとことば遊び、そして何よりも野田の存在感に惹かれ、その舞台を観続けてきた。遊眠社解散後にロンドン留学、帰国後に結成したNODA MAPは、前よりは取り易くなったものの、今もなかなかチケットが買えない人気。お気楽夫婦も毎回トライしながら実際に観に行けたのは6割程度。それでも毎回観に行こうと思わせる魅力がある。
 ある週末、NODA MAP 第16回公演『南へ』を観た。会場は野田が芸術監督に就任した東京芸術劇場。劇場前にはブロードウェーもかくやという出演者の巨大な顔写真がずらりと並ぶ。NODA MAPの基本はプロデュース公演。毎回、公演毎に役者を集め上演する。これまでの出演者は、堤真一、宮沢りえ、広末涼子、大竹しのぶ、松たか子などのビッグネームはもちろん、かつて遊眠社と人気を競った小劇団である第三舞台の看板役者だった筧利夫や勝村政信、自由劇場の主宰だった串田和美、解散したM.O.P.の人気女優キムラ緑子、大人計画の阿部サダヲなど、芝居好きにとっては毎回垂涎の豪華でありかつ通好みの多才で多彩なキャスティング。
ある週末、NODA MAP 第16回公演『南へ』を観た。会場は野田が芸術監督に就任した東京芸術劇場。劇場前にはブロードウェーもかくやという出演者の巨大な顔写真がずらりと並ぶ。NODA MAPの基本はプロデュース公演。毎回、公演毎に役者を集め上演する。これまでの出演者は、堤真一、宮沢りえ、広末涼子、大竹しのぶ、松たか子などのビッグネームはもちろん、かつて遊眠社と人気を競った小劇団である第三舞台の看板役者だった筧利夫や勝村政信、自由劇場の主宰だった串田和美、解散したM.O.P.の人気女優キムラ緑子、大人計画の阿部サダヲなど、芝居好きにとっては毎回垂涎の豪華でありかつ通好みの多才で多彩なキャスティング。
 今回も早々にNODA MAP初出演の蒼井優と、13回公演『キル』に続いて2度目の主演である妻夫木聡という魅力の組合せを発表。渡辺いっけい、銀粉蝶、チョウソンハなどが脇を固める。舞台は富士山を思わせる火山。現代の観測所、そして江戸らしき時代。蒼井優と妻夫木聡の演技も、セリフも悪くない。2人の存在感は際立ち、いわゆる役者オーラが溢れ、キャラクターとしても魅力がある。折りたたみのパイプ椅子だけを使って、時にはテレビに、時には輿に、時には地鳴りの小道具として使う演出も秀逸。まるで歌舞伎のような小気味の良い場面転換も素晴らしい。しかし、物語は相変わらず複雑に交錯し、たたみかけるようなことば遊びが鳴りを潜めた分、観客はストーリーや物語の意味を追い過ぎてしまうことになる。意味だけを追わなくても楽しむことができる野田の世界の輝きが褪せて見えた。
今回も早々にNODA MAP初出演の蒼井優と、13回公演『キル』に続いて2度目の主演である妻夫木聡という魅力の組合せを発表。渡辺いっけい、銀粉蝶、チョウソンハなどが脇を固める。舞台は富士山を思わせる火山。現代の観測所、そして江戸らしき時代。蒼井優と妻夫木聡の演技も、セリフも悪くない。2人の存在感は際立ち、いわゆる役者オーラが溢れ、キャラクターとしても魅力がある。折りたたみのパイプ椅子だけを使って、時にはテレビに、時には輿に、時には地鳴りの小道具として使う演出も秀逸。まるで歌舞伎のような小気味の良い場面転換も素晴らしい。しかし、物語は相変わらず複雑に交錯し、たたみかけるようなことば遊びが鳴りを潜めた分、観客はストーリーや物語の意味を追い過ぎてしまうことになる。意味だけを追わなくても楽しむことができる野田の世界の輝きが褪せて見えた。
 「う〜ん、面白かったけど、惜しい!って感じだねぇ」観終わった後、会場からの道すがらお気楽夫婦の芝居談義。妻の意見も私と大差なさそうだ。北から来たものとか、途切れた天皇家とか、物語やことばの深さも脚本の切れ味も今ひとつ中途半端だったと伝えると、「そうなんだよねぇ。私も最初寝ちゃいそうになった」おいおいっ!「この前観たカトケンの方が安心して観られたねぇ」ウェルメイドな芝居で定評のある加藤健一事務所の公演と比較するには芝居の方向性が全く違うけれど、どちらも2人が長く観続けてきた舞台。どちらも当りもハズレもあるのは仕方ない。けれど、北を寒さ、厳しさの象徴とするならば、南とはどこなのか。暖かく、優しく、穏やかなものの象徴だとするならば、かつて渡ったロンドンのように、野田秀樹には北へ向って欲しい。野田秀樹という天才が目指す場所は、天才にとっても簡単には到達できない場所であって欲しい。その過程を観客にいつまでも観させて欲しい。
「う〜ん、面白かったけど、惜しい!って感じだねぇ」観終わった後、会場からの道すがらお気楽夫婦の芝居談義。妻の意見も私と大差なさそうだ。北から来たものとか、途切れた天皇家とか、物語やことばの深さも脚本の切れ味も今ひとつ中途半端だったと伝えると、「そうなんだよねぇ。私も最初寝ちゃいそうになった」おいおいっ!「この前観たカトケンの方が安心して観られたねぇ」ウェルメイドな芝居で定評のある加藤健一事務所の公演と比較するには芝居の方向性が全く違うけれど、どちらも2人が長く観続けてきた舞台。どちらも当りもハズレもあるのは仕方ない。けれど、北を寒さ、厳しさの象徴とするならば、南とはどこなのか。暖かく、優しく、穏やかなものの象徴だとするならば、かつて渡ったロンドンのように、野田秀樹には北へ向って欲しい。野田秀樹という天才が目指す場所は、天才にとっても簡単には到達できない場所であって欲しい。その過程を観客にいつまでも観させて欲しい。
「なぁ〜んか難しいこと言ってるけど、おもしろいのがイチバンってことだと思うよ」妻はいつも分かり易い。
 お気楽夫婦が住むマンションは、世田谷の外れの街の駅近くにある100戸弱の規模。2基あるエレベータで住民同士が乗り合わせても、挨拶をするのは半数程度。それも元気に声に出して挨拶する子供たち以外は、むにゃむにゃと口の中でことばにならない声を出したり、軽く会釈する人がほとんど。けれど不思議なことに、管理室や掃除のおじちゃんには誰もが「おはようございます」ときちんと挨拶し、出かけて行く。決して住民に社会性や交流能力が欠如している訳ではない。住民同士の多くは顔見知りでもないし、集会室がある訳でもなく、管理組合の総会があっても参加するのは20人程度。2〜300人の住民が最小限の交流で同じ建物の中に暮らしている。こうして書きながら、同じマンションに住んでいる人数も知らないという事実に気付く、典型的な都市型集合住宅。
お気楽夫婦が住むマンションは、世田谷の外れの街の駅近くにある100戸弱の規模。2基あるエレベータで住民同士が乗り合わせても、挨拶をするのは半数程度。それも元気に声に出して挨拶する子供たち以外は、むにゃむにゃと口の中でことばにならない声を出したり、軽く会釈する人がほとんど。けれど不思議なことに、管理室や掃除のおじちゃんには誰もが「おはようございます」ときちんと挨拶し、出かけて行く。決して住民に社会性や交流能力が欠如している訳ではない。住民同士の多くは顔見知りでもないし、集会室がある訳でもなく、管理組合の総会があっても参加するのは20人程度。2〜300人の住民が最小限の交流で同じ建物の中に暮らしている。こうして書きながら、同じマンションに住んでいる人数も知らないという事実に気付く、典型的な都市型集合住宅。