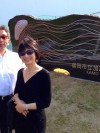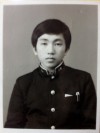お手軽レシピ♬「サラダランチ弁当」
2014年 6 月14日(土)
 妻のランチは、カロリーメイトなどのサプリメントを食べるだけ、ということが多かった。そんな日々を続ける内に、「野菜が足りない!」と言いだした。野菜サラダの弁当を作って持って行こう!と意気込んだものの、初日から挫折。サラダランチ弁当を作るのは、朝が早い私の担当となった。目の前にあるJAの直売所で、毎週末に1週間分の野菜を買込み、だいたいのローテーションを考える。大根、ニンジンなどの根野菜や、水が出にくいプティトマト、パプリカ、ズッキーニ、ラディッシュなど、世田谷産の野菜中心をたっぷり買っても1,000円前後。形が不揃いだったり、色が悪かったりもするけれど、新鮮で美味しい。日持ちもする。今週は宍戸さんのニンジン、杉田さんのキャベツなどと、生産者の名前を確認しながら選ぶのも楽しい。
妻のランチは、カロリーメイトなどのサプリメントを食べるだけ、ということが多かった。そんな日々を続ける内に、「野菜が足りない!」と言いだした。野菜サラダの弁当を作って持って行こう!と意気込んだものの、初日から挫折。サラダランチ弁当を作るのは、朝が早い私の担当となった。目の前にあるJAの直売所で、毎週末に1週間分の野菜を買込み、だいたいのローテーションを考える。大根、ニンジンなどの根野菜や、水が出にくいプティトマト、パプリカ、ズッキーニ、ラディッシュなど、世田谷産の野菜中心をたっぷり買っても1,000円前後。形が不揃いだったり、色が悪かったりもするけれど、新鮮で美味しい。日持ちもする。今週は宍戸さんのニンジン、杉田さんのキャベツなどと、生産者の名前を確認しながら選ぶのも楽しい。
 レシピは簡単なのが基本。見た目の色合いを気にすることと、飽きないようにバリエーションを付けることが必須。その日のインスピレーションで、野菜の組合せや味付け、切り方を変える。例えば、キャロットラペ。フランスの常備菜。ニンジンの皮を剥き、スライサーで細切りにし、塩を振って味が沁み易いように軽く手で絞る。そこにオリーブオイル、ワインビネガー、レモン汁(もちろんボトルのもの)、ハチミツ、ブラックペッパー、パセリなどを適宜入れて混ぜて、冷蔵庫で冷やし、しっとりさせてから弁当箱へ詰め込む。アーモンドスライス、干しぶどう等、酒のつまみで余ったモノを加える場合もある。作って5時間後くらいに食べる頃には味が馴染んでいるはず。多めに作っても酒のつまみになる。白ワインに良く合う♬
レシピは簡単なのが基本。見た目の色合いを気にすることと、飽きないようにバリエーションを付けることが必須。その日のインスピレーションで、野菜の組合せや味付け、切り方を変える。例えば、キャロットラペ。フランスの常備菜。ニンジンの皮を剥き、スライサーで細切りにし、塩を振って味が沁み易いように軽く手で絞る。そこにオリーブオイル、ワインビネガー、レモン汁(もちろんボトルのもの)、ハチミツ、ブラックペッパー、パセリなどを適宜入れて混ぜて、冷蔵庫で冷やし、しっとりさせてから弁当箱へ詰め込む。アーモンドスライス、干しぶどう等、酒のつまみで余ったモノを加える場合もある。作って5時間後くらいに食べる頃には味が馴染んでいるはず。多めに作っても酒のつまみになる。白ワインに良く合う♬
 コールスローも定番。新鮮元気な世田谷産キャベツを使って、カンタンにできる。細かく切ったキャベツを軽く塩揉み。水を切って、コーン入りツナ缶を混ぜ、塩胡椒。その後は、マヨネーズや市販のドレッシングで和える。妻の好みは薄味、油分少なめ。塩胡椒を多めに、ドレッシングは少なめにして、野菜本来の味が前に出るように心がける。バリエーションが限りなく広がるのが蒸し野菜サラダ。食べ易い大きさにカットした野菜に塩胡椒、オリーブオイルで下味を付け、ココット鍋に入れ、電子レンジで1分前後蒸す。いったん取り出し、火の通りにくいものは再度蒸し直すが、野菜は固めに仕上げるのが基本。そして冷ましつつ、市販のドレッシングで和える。ドレッシングは何種類か用意してあり、味付けのバリエーションに留意する。
コールスローも定番。新鮮元気な世田谷産キャベツを使って、カンタンにできる。細かく切ったキャベツを軽く塩揉み。水を切って、コーン入りツナ缶を混ぜ、塩胡椒。その後は、マヨネーズや市販のドレッシングで和える。妻の好みは薄味、油分少なめ。塩胡椒を多めに、ドレッシングは少なめにして、野菜本来の味が前に出るように心がける。バリエーションが限りなく広がるのが蒸し野菜サラダ。食べ易い大きさにカットした野菜に塩胡椒、オリーブオイルで下味を付け、ココット鍋に入れ、電子レンジで1分前後蒸す。いったん取り出し、火の通りにくいものは再度蒸し直すが、野菜は固めに仕上げるのが基本。そして冷ましつつ、市販のドレッシングで和える。ドレッシングは何種類か用意してあり、味付けのバリエーションに留意する。
 冬は大根サラダが多くなる。細切りにした大根に塩を振り、キッチンタオルで軽く水分を絞る。そこに缶詰の貝柱。塩胡椒。マヨネーズ系の味でも、柑橘系のドレッシング、ゴマドレッシングでもOK。味付けによって乾燥刻み柚子、サラダ用ジャコなどを混ぜる場合もあるし、彩り良くするためにラディッシュを加えたり、乾燥パセリを加えたり。いずれも昼頃にはしっとり美味しくなっているはず。リンゴや梨などの季節のフルーツを使ったサラダもいける。果物を小口に切り、塩水に浸し色止めをして、その後に水分を拭き取り、イタリアンなどの香辛料が多めのドレッシングと、クリームチーズとブラックペッパー、そしてレモン汁と和える。仕上げにパセリをぱらり。柑橘系のドレッシングでも合う。ワインにも合う。
冬は大根サラダが多くなる。細切りにした大根に塩を振り、キッチンタオルで軽く水分を絞る。そこに缶詰の貝柱。塩胡椒。マヨネーズ系の味でも、柑橘系のドレッシング、ゴマドレッシングでもOK。味付けによって乾燥刻み柚子、サラダ用ジャコなどを混ぜる場合もあるし、彩り良くするためにラディッシュを加えたり、乾燥パセリを加えたり。いずれも昼頃にはしっとり美味しくなっているはず。リンゴや梨などの季節のフルーツを使ったサラダもいける。果物を小口に切り、塩水に浸し色止めをして、その後に水分を拭き取り、イタリアンなどの香辛料が多めのドレッシングと、クリームチーズとブラックペッパー、そしてレモン汁と和える。仕上げにパセリをぱらり。柑橘系のドレッシングでも合う。ワインにも合う。
「うわぁ、こんなにヴォリュームあるんだぁ」調理中のボウルを覗き込み、妻が驚く。ピシッと閉じる密閉容器が弁当箱代わり。見た目よりもかなり入るし、中途半端に残っても嫌なので、ぎゅぎゅっと詰める。2種類のサラダが入った弁当箱は、毎日ずっしり重い。サプリメントやベーグルと一緒に食べているらしいが、小食の妻なら満足な量のランチ。健康的かつ経済的で一石二鳥な弁当。そして私はと言えば、時間と戦いながら手際良く工夫して作るのが毎日楽しく、すっかり趣味の世界に突入したサラダランチ弁当、間もなく3年目に突入!