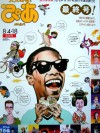 初めて『ぴあ』を手に取ったのは、1976年5月。表紙はアラン・ドロンの『ル・ジタン』。首都圏のエンタテインメント情報を網羅したその誌面に圧倒された。映画館が3館しかなかった街から上京してきたワカモノにとって、『ぴあ』を通して目の前に広がる東京という都市はエンタテインメントの大海だった。『ぴあ』という海図と羅針盤がなければ、とても大海原に漕ぎだせそうもなかった。その海図には小さな映画館もロードショー館もフラットに掲載されていた。権威的な視点はなかった。たまに(というか割と頻繁に)誤植があったし、それを発見してはその手作り感を喜んでいた。押し付けられた情報を受け取るのではなく、自ら情報を探すことが楽しみだった。行きたいと思う公演情報をラインマーカーで囲んだ。誰を誘おうかと妄想に近い計画を立てながらも、結局1人で名画座に足を運んだりしていた。
初めて『ぴあ』を手に取ったのは、1976年5月。表紙はアラン・ドロンの『ル・ジタン』。首都圏のエンタテインメント情報を網羅したその誌面に圧倒された。映画館が3館しかなかった街から上京してきたワカモノにとって、『ぴあ』を通して目の前に広がる東京という都市はエンタテインメントの大海だった。『ぴあ』という海図と羅針盤がなければ、とても大海原に漕ぎだせそうもなかった。その海図には小さな映画館もロードショー館もフラットに掲載されていた。権威的な視点はなかった。たまに(というか割と頻繁に)誤植があったし、それを発見してはその手作り感を喜んでいた。押し付けられた情報を受け取るのではなく、自ら情報を探すことが楽しみだった。行きたいと思う公演情報をラインマーカーで囲んだ。誰を誘おうかと妄想に近い計画を立てながらも、結局1人で名画座に足を運んだりしていた。
当時、駿河台にあるアテネ・フランセに通っていた私は、ある日教室の窓から『ぴあ』の看板を発見した。身近な存在だった『ぴあ』にますます親近感が湧いたが、こんな小さなビル(の一室?)で作っているのかと驚きもした。今思えばTwitterの先駆けのようなはみだしYOUとPIAも、あまくさまゆみが描くコオニちゃんのぱらぱらマンガも、欄外のはみだし情報も、誌面の隅々まで目を通した。以降、1980年代前半まで、毎号のように購入しては街に出かけるという『ぴあ』と私の蜜月時代が続いた。『ぴあ』によって演劇に目覚め、唐十郎の状況劇場、自転車キンクリート、加藤健一事務所の芝居と出会った。デビューしたばかりのサザンのライブを観に江ノ島マリーナに出掛けた。毎年、元旦は内田裕也プレゼンツの年越しライブ会場で迎えた。夏には野外フェスで身体を焼いた。そんな学生時代を過ごした私の隣には『ぴあ』があった。
大学を卒業した私が入社したのは、某大手百貨店。情報発信基地を標榜した当時の人気企業であり、糸井重里のコピー「不思議、大好き。」などで知られる時代の寵児だった。セゾン美術館、スタジオ200、アールヴィヴァンなどの文化施設を持ち、「六本木WAVE」や「無印良品」などの新たな業態を創出した。文学者でもあった経営トップの経営方針は「感性の経営」と呼ばれ、文化事業を重視した企業風土に惹かれて入社した会社だった。けれども当然のことながら根幹は流通業だった。そして1986年夏、縁あって『ぴあ』を発行するぴあという会社に入ることになった。ぴあという会社には、『ぴあ』的世界で仕事も遊びも楽しんでいるヤツらが大勢いた。その当時のぴあのキャッチコピーに「ぼくらは世界で一番面白い街に住んでいる」というのがあったが、それを体現しているのは、ぴあで働くスタッフたちそのものだった。
『ぴあ』は、客観性、網羅性、検索性、携帯性を持つ情報誌だった。そこにチケット販売という機能が加わり、ライブエンタテインメントの「場」をも提供することになった。チケットぴあだ。入社した私は、流通業での経験を活かし、チケットぴあの店舗開拓を担当した。北海道から九州、台湾まで、出張日数は年間100日を超えた。そして出張の合間に、芝居を楽しみ、コンサートに行き、美術館を巡り、映画を観た。傍らにはもちろん、いつも『ぴあ』があった。その後も幅広い業務を担当した。1996年のアトランタオリンピック、2002年の上海展開など海外出張も多かった。そして、20年ほどお世話になった後、ぴあを離れることになった。けれど、その後も『ぴあ』的な生活は変わらなかった。
2011年7月21日、『ぴあ』の最終号が発売された。多くの読者やぴあOBや現役の社員たちがFacebookやTwitterで盛んに惜別の思いを発信した。時代は変わった。役割を全うした。お世話になった。ありがとう…。
2011年現在、網羅性と検索性、携帯性を持ち、チケット予約やクーポンの機能まで持つスマートフォンが世の中を席巻している。確かに今や『ぴあ』の存在意義は失われた。それでも、私の『ぴあ』的生活は変わらない。楽しいことや美味しいモノに貪欲で、軽いフットワークでライブエンタテインメントに出掛けて行く。
『ぴあ』のスピリッツは、今でも私の中にある。きっとこれからもずっとある。ぼくらは世界で一番面白い街に住んでいる。

 例えば今年の7月なら1日。毎月最初の営業日、その店の電話はなかなか繋がらない。ランチ予約の電話が殺到するためだ。オーナーシェフの本城さんは、たん熊北店やパリの日本大使館で料理の腕を振るった後、2009年に独立し「用賀 本城」を開店。すぐに予約が取りにくい人気店となった。特にランチは予約が殺到。席を押さえるには何ヶ月も待たなければいけない状況となった。そこで窮余の策として、1ヶ月分の予約を前々月の第1営業日に受付けることした。本城ファンのお気楽夫婦。夜は何度もお邪魔しているものの、ランチは未訪問。お得だと評判のランチに行ってみたいとずっと思っていた。かと言って電話を掛け続ける時間はない。友人たちの間でそんな話題になった時に、神の声。「私が直接お店に行って予約するよ♬」用賀に住むスカッシュ仲間のステキな提案だ。
例えば今年の7月なら1日。毎月最初の営業日、その店の電話はなかなか繋がらない。ランチ予約の電話が殺到するためだ。オーナーシェフの本城さんは、たん熊北店やパリの日本大使館で料理の腕を振るった後、2009年に独立し「用賀 本城」を開店。すぐに予約が取りにくい人気店となった。特にランチは予約が殺到。席を押さえるには何ヶ月も待たなければいけない状況となった。そこで窮余の策として、1ヶ月分の予約を前々月の第1営業日に受付けることした。本城ファンのお気楽夫婦。夜は何度もお邪魔しているものの、ランチは未訪問。お得だと評判のランチに行ってみたいとずっと思っていた。かと言って電話を掛け続ける時間はない。友人たちの間でそんな話題になった時に、神の声。「私が直接お店に行って予約するよ♬」用賀に住むスカッシュ仲間のステキな提案だ。

 ある週末、スカッシュ仲間5人が用賀 本城のカウンタ席に並んだ。用賀在住のパン教室の先生が、開店と同時に店に飛び込んで予約してくれたおかげ。「いらっしゃいませ…え、どうされましたん?」松葉杖の妻の姿に驚きながらも、カウンタの向こうで本城さんが笑顔で迎えてくれた。「ステキなお店ねぇ♡」本城初訪問の元CAのマダムが呟く。その直感は素晴らしい。「お久しぶりです」若手建築家が朗らかに本城さんと挨拶を交わす。彼は夫婦でランチに訪れて以来らしい。そんなメンバーはヤマガタサンダンデロに続き、同じ顔ぶれ。待望の本城ランチを味わうのに相応しい、飲んべで、食いしん坊で、何より一緒に食事をするのに楽しいメンバーだ。お願いするのは会席コース2,625円。妻を除きビールで乾杯。
ある週末、スカッシュ仲間5人が用賀 本城のカウンタ席に並んだ。用賀在住のパン教室の先生が、開店と同時に店に飛び込んで予約してくれたおかげ。「いらっしゃいませ…え、どうされましたん?」松葉杖の妻の姿に驚きながらも、カウンタの向こうで本城さんが笑顔で迎えてくれた。「ステキなお店ねぇ♡」本城初訪問の元CAのマダムが呟く。その直感は素晴らしい。「お久しぶりです」若手建築家が朗らかに本城さんと挨拶を交わす。彼は夫婦でランチに訪れて以来らしい。そんなメンバーはヤマガタサンダンデロに続き、同じ顔ぶれ。待望の本城ランチを味わうのに相応しい、飲んべで、食いしん坊で、何より一緒に食事をするのに楽しいメンバーだ。お願いするのは会席コース2,625円。妻を除きビールで乾杯。

 先付けは、そうめん南瓜の和え物。胡麻や胡桃の優しい味付け、そうめん南瓜の歯応え、それらを山椒の香りが引き締める。旨い。続いてトマトのジュレの上に、山芋とアオリイカが美しく盛られた一品。ガラスの器が清々しい。思わず唸る味。んっ旨いっ。これは日本酒でしょう!ということで、辛口の冷酒をお願いする。飲み始めるとセーブできない己を知るメンバーは、最初は躊躇いながらも追随。アオリイカを味わい、きりりと冷えた酒をぐびりと含めば笑顔が零れる。椀の中で美しく鱧が微笑む。向付の鮮やかな深緑の皿の上で鮪の赤が映える。夜のコース料理と同様に一皿一皿が丁寧な仕事。これがランチのメニューとはとても思えないゼータクな料理が供される。
先付けは、そうめん南瓜の和え物。胡麻や胡桃の優しい味付け、そうめん南瓜の歯応え、それらを山椒の香りが引き締める。旨い。続いてトマトのジュレの上に、山芋とアオリイカが美しく盛られた一品。ガラスの器が清々しい。思わず唸る味。んっ旨いっ。これは日本酒でしょう!ということで、辛口の冷酒をお願いする。飲み始めるとセーブできない己を知るメンバーは、最初は躊躇いながらも追随。アオリイカを味わい、きりりと冷えた酒をぐびりと含めば笑顔が零れる。椀の中で美しく鱧が微笑む。向付の鮮やかな深緑の皿の上で鮪の赤が映える。夜のコース料理と同様に一皿一皿が丁寧な仕事。これがランチのメニューとはとても思えないゼータクな料理が供される。

 「器も、盛付けも、ほんと美しいよねぇ」パン教室の先生が感嘆する。2本目の酒は違う銘柄でお願いすると、涼しげなガラスの徳利と猪口がカウンタに並ぶ。「キレ〜!セットで持って帰りたぁ〜い」「ご近所だからって、ホントに持って帰っちゃだめだよ」「そしたらご自宅まで取りに伺います」メンバーと本城さんのやり取りの息も合ってきた。揚げ物の皿には青紅葉。これまた美しい。調子に乗って3本目のお銚子をお願いする。新たな銘柄で、新たなガラスの徳利と猪口。ぐびり。くぅ〜っ!幸せである。その後に炊き合わせ、ご飯、水菓子と続く。この店のランチは、噂以上に凄い。敢えて繰り返して言う。これで2,625円。料理、器、店の佇まい、気遣い込み。とてもこの価格で出せる店は他にはない。申し訳ないぐらい。「ほんま、ランチは採算合いません」サービス担当の奥さまがこっそりと、それでも笑顔で呟く。
「器も、盛付けも、ほんと美しいよねぇ」パン教室の先生が感嘆する。2本目の酒は違う銘柄でお願いすると、涼しげなガラスの徳利と猪口がカウンタに並ぶ。「キレ〜!セットで持って帰りたぁ〜い」「ご近所だからって、ホントに持って帰っちゃだめだよ」「そしたらご自宅まで取りに伺います」メンバーと本城さんのやり取りの息も合ってきた。揚げ物の皿には青紅葉。これまた美しい。調子に乗って3本目のお銚子をお願いする。新たな銘柄で、新たなガラスの徳利と猪口。ぐびり。くぅ〜っ!幸せである。その後に炊き合わせ、ご飯、水菓子と続く。この店のランチは、噂以上に凄い。敢えて繰り返して言う。これで2,625円。料理、器、店の佇まい、気遣い込み。とてもこの価格で出せる店は他にはない。申し訳ないぐらい。「ほんま、ランチは採算合いません」サービス担当の奥さまがこっそりと、それでも笑顔で呟く。
「みんなぁ、次は10月だよぉ〜♬また予約しちゃうよぉ〜♡」パン教室の先生はすっかり本城ランチがお気に入りのご様子。主婦としてはランチの方が気兼ねなく楽しめるということもあるらしい。了解。こんなに価値のあるランチはそう味わえない。他のメンバーも笑顔で頷く。秋の味覚を楽しみにしよう。「でも、やっぱり夜にも来なきゃね」妻が呟く。それも了解。松葉杖が取れた頃に、完治のお祝いで伺おう。秋に向けて、楽しい予定がまたひとつ。あ、ふたつ。
■食いしん坊夫婦の御用達へ 「用賀 本城」
 読むのを楽しみにしていた作品があった。有川浩の『図書館戦争』シリーズ。作者の有川浩は最近公開された映画『阪急電車』の原作者。映画の評判は今ひとつだったけれど、それによって原作の魅力が削がれるものでもない。小説作品としての『阪急電車』は、登場人物たちの魅力が短いエピソードの中で輝く、実に良い作品だった。その1冊を読んだ後、お気楽夫婦はあっという間にファンになり、文庫化された全ての作品を読んでいた。その有川浩がブレイクしたきっかけになったのが『図書館戦争』シリーズだと聞いていた。それにしても、図書館と戦争という異質なことばがなぜ結びついているのか?図書館を舞台にしている戦争なのか?図書館同士の争いの物語なのか?物語の内容に予備知識を持たずに読み始めた。…そして、はまった。
読むのを楽しみにしていた作品があった。有川浩の『図書館戦争』シリーズ。作者の有川浩は最近公開された映画『阪急電車』の原作者。映画の評判は今ひとつだったけれど、それによって原作の魅力が削がれるものでもない。小説作品としての『阪急電車』は、登場人物たちの魅力が短いエピソードの中で輝く、実に良い作品だった。その1冊を読んだ後、お気楽夫婦はあっという間にファンになり、文庫化された全ての作品を読んでいた。その有川浩がブレイクしたきっかけになったのが『図書館戦争』シリーズだと聞いていた。それにしても、図書館と戦争という異質なことばがなぜ結びついているのか?図書館を舞台にしている戦争なのか?図書館同士の争いの物語なのか?物語の内容に予備知識を持たずに読み始めた。…そして、はまった。
 5ヶ月連続で角川文庫から刊行され、6月までに本編4冊が既に発刊された。そして全てがベストセラーランキングの上位。7月、8月にサイドストーリーを描いた別冊が刊行され、シリーズが終了する予定だ。その角川書店の策略に、見事に絡めとられた。まずは、4月に刊行されたシリーズ1作目『図書館戦争』で、その設定の奇抜さと大胆さ、そして物語の緻密な構成と、何よりも登場人物たちに魅了されてしまった。2作目『図書館内乱』で、脇役にスポットライトが当てられたエピソードによって、物語にさらなる深みと広がりが生まれ、物語の世界にずぶずぶと浸った。物語の展開に感情移入しまくり。この頃になるとご贔屓のキャラクターが生まれ、その登場人物の視点でストーリーをハラハラしながら見守った。
5ヶ月連続で角川文庫から刊行され、6月までに本編4冊が既に発刊された。そして全てがベストセラーランキングの上位。7月、8月にサイドストーリーを描いた別冊が刊行され、シリーズが終了する予定だ。その角川書店の策略に、見事に絡めとられた。まずは、4月に刊行されたシリーズ1作目『図書館戦争』で、その設定の奇抜さと大胆さ、そして物語の緻密な構成と、何よりも登場人物たちに魅了されてしまった。2作目『図書館内乱』で、脇役にスポットライトが当てられたエピソードによって、物語にさらなる深みと広がりが生まれ、物語の世界にずぶずぶと浸った。物語の展開に感情移入しまくり。この頃になるとご贔屓のキャラクターが生まれ、その登場人物の視点でストーリーをハラハラしながら見守った。
 3作め『図書館危機』を読み始めた頃には広がる物語の裾野の大きさに驚きながら、涙するエピソードに心を震わせる。差別用語の取扱を巡るエピソードに背筋がひやっとする。表現の自由を脅かす公的組織の検閲から、図書館という組織により表現の自由を守るという架空の物語に、現実世界が重なってくる。そして第4作『図書館革命』での大団円。読み終えてしまう淋しさを感じながら、物語世界がどこかで続いているという確信に近い幻想を覚えるほど、登場人物たちが物語の中で生きている。登場人物のひとりひとりが、読者に過ぎない私の頭の中を動き回っている。それも、全員が身近なキャラクターとして。
3作め『図書館危機』を読み始めた頃には広がる物語の裾野の大きさに驚きながら、涙するエピソードに心を震わせる。差別用語の取扱を巡るエピソードに背筋がひやっとする。表現の自由を脅かす公的組織の検閲から、図書館という組織により表現の自由を守るという架空の物語に、現実世界が重なってくる。そして第4作『図書館革命』での大団円。読み終えてしまう淋しさを感じながら、物語世界がどこかで続いているという確信に近い幻想を覚えるほど、登場人物たちが物語の中で生きている。登場人物のひとりひとりが、読者に過ぎない私の頭の中を動き回っている。それも、全員が身近なキャラクターとして。
 芥川賞に象徴される“純文学”という死語に近いジャンルがある。“大衆文学”というこれまた死語になっているジャンルに対する直木賞との比較において、純文学が優越的な見方をされることがある。さらには、ライトノベルというジャンルに対しては卑下する見方すらあり、マンガに至っては同じテーブルの上に載せてさえもらえない。芸術と娯楽という2極は対立するものではないし、商業的であるから否定されるものでもない。作者の有川浩がライトノベル出身の作者であることや、この『図書館戦争』シリーズの表紙を見て、手に取るのを躊躇う人がいるかもしれない。けれど、騙されたと思って読んで欲しい。
芥川賞に象徴される“純文学”という死語に近いジャンルがある。“大衆文学”というこれまた死語になっているジャンルに対する直木賞との比較において、純文学が優越的な見方をされることがある。さらには、ライトノベルというジャンルに対しては卑下する見方すらあり、マンガに至っては同じテーブルの上に載せてさえもらえない。芸術と娯楽という2極は対立するものではないし、商業的であるから否定されるものでもない。作者の有川浩がライトノベル出身の作者であることや、この『図書館戦争』シリーズの表紙を見て、手に取るのを躊躇う人がいるかもしれない。けれど、騙されたと思って読んで欲しい。
この作品は、素晴らしくステキなエンタテインメントだ。
物語の行間を読者に委ねるだけではなく、登場人物たちの呟きを敢えて文字として書く。マンガの小さな吹き出しのように。巻頭に登場人物たちのシルエット付きの紹介文がある。会話に勢いがあり、話ことばの選択にリアリティがある。たぶん賛否両論も、ある。けれど、各作品の巻末にある作者と故児玉清さんとの対談に、この作品の魅力が増す2人のことばが溢れている。
「まだあと2冊出るんだね」すっかり有川ファンとなった妻。彼女はまだ3作めを読んでいる途中。ネタバレしないように、ていねいに丁寧に記事を書いた。「バレたってヘーキだよ!」巻末の解説から読み始める妻。最後の1行を楽しみにする私。読書スタイルは違うけれど、この作品世界に魅せられたのは同じだ。




*素晴らしくステキなエンタテインメント♬ おススメです♡
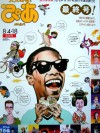 初めて『ぴあ』を手に取ったのは、1976年5月。表紙はアラン・ドロンの『ル・ジタン』。首都圏のエンタテインメント情報を網羅したその誌面に圧倒された。映画館が3館しかなかった街から上京してきたワカモノにとって、『ぴあ』を通して目の前に広がる東京という都市はエンタテインメントの大海だった。『ぴあ』という海図と羅針盤がなければ、とても大海原に漕ぎだせそうもなかった。その海図には小さな映画館もロードショー館もフラットに掲載されていた。権威的な視点はなかった。たまに(というか割と頻繁に)誤植があったし、それを発見してはその手作り感を喜んでいた。押し付けられた情報を受け取るのではなく、自ら情報を探すことが楽しみだった。行きたいと思う公演情報をラインマーカーで囲んだ。誰を誘おうかと妄想に近い計画を立てながらも、結局1人で名画座に足を運んだりしていた。
初めて『ぴあ』を手に取ったのは、1976年5月。表紙はアラン・ドロンの『ル・ジタン』。首都圏のエンタテインメント情報を網羅したその誌面に圧倒された。映画館が3館しかなかった街から上京してきたワカモノにとって、『ぴあ』を通して目の前に広がる東京という都市はエンタテインメントの大海だった。『ぴあ』という海図と羅針盤がなければ、とても大海原に漕ぎだせそうもなかった。その海図には小さな映画館もロードショー館もフラットに掲載されていた。権威的な視点はなかった。たまに(というか割と頻繁に)誤植があったし、それを発見してはその手作り感を喜んでいた。押し付けられた情報を受け取るのではなく、自ら情報を探すことが楽しみだった。行きたいと思う公演情報をラインマーカーで囲んだ。誰を誘おうかと妄想に近い計画を立てながらも、結局1人で名画座に足を運んだりしていた。














