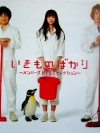武蔵野市吉祥寺。情報誌が実施する「住みたい街」アンケートでトップランキングの常連となる街。井の頭公園付近をはじめとした武蔵野の緑と水のある環境や、充実した商業施設、飲食店、そのバランスの良さが人気の理由。吉祥寺は今、ロンロンがアトレに名前を変えリニューアルオープンしたり、伊勢丹吉祥寺店が撤退した後にcoppice KICHIJOJI(コピス吉祥寺)というショッピングビルが誕生したりと何かと話題。中央線沿線の街の中で、立川に逆転された街の集客力を高めるために街をあげて取り組んでいる。老舗焼鳥屋「いせや」の建替えも終わり営業再開。ハーモニカ横町も一時の停滞から小規模立ち飲み店が増え賑わいを取り戻した。
武蔵野市吉祥寺。情報誌が実施する「住みたい街」アンケートでトップランキングの常連となる街。井の頭公園付近をはじめとした武蔵野の緑と水のある環境や、充実した商業施設、飲食店、そのバランスの良さが人気の理由。吉祥寺は今、ロンロンがアトレに名前を変えリニューアルオープンしたり、伊勢丹吉祥寺店が撤退した後にcoppice KICHIJOJI(コピス吉祥寺)というショッピングビルが誕生したりと何かと話題。中央線沿線の街の中で、立川に逆転された街の集客力を高めるために街をあげて取り組んでいる。老舗焼鳥屋「いせや」の建替えも終わり営業再開。ハーモニカ横町も一時の停滞から小規模立ち飲み店が増え賑わいを取り戻した。
 お気楽夫婦の住む街から吉祥寺までは、バスでのんびり30分程。マンションの窓から吉祥寺駅周辺のビル群が見える程の距離。ある週末、2人は井の頭公園の紅葉見物に出かけた。井の頭公園は正式名称「井の頭恩賜公園」。大正6年に開園した日本で初めての郊外型公園だと言う。2017年に開園100周年を迎えるに当たって、武蔵野市をはじめとした行政や市民及び関係団体が集まり、井の頭恩賜公園100年実行委員会を設置。その事業の一環として2008年より「井の頭公園アートマーケッツ(ART*MRT)」を実施している。大道芸人やパフォーマーに登録してもらい、土日の公園敷地内でパフォーマンスを行ってもらおうというもの。七井橋を渡りボート乗り場を行き過ぎ、ペパカフェフォレストの前で、お気楽夫婦が散歩中に偶然出会ったのは、Mr.Dai(ミスター・ダイ)という大道芸人。
お気楽夫婦の住む街から吉祥寺までは、バスでのんびり30分程。マンションの窓から吉祥寺駅周辺のビル群が見える程の距離。ある週末、2人は井の頭公園の紅葉見物に出かけた。井の頭公園は正式名称「井の頭恩賜公園」。大正6年に開園した日本で初めての郊外型公園だと言う。2017年に開園100周年を迎えるに当たって、武蔵野市をはじめとした行政や市民及び関係団体が集まり、井の頭恩賜公園100年実行委員会を設置。その事業の一環として2008年より「井の頭公園アートマーケッツ(ART*MRT)」を実施している。大道芸人やパフォーマーに登録してもらい、土日の公園敷地内でパフォーマンスを行ってもらおうというもの。七井橋を渡りボート乗り場を行き過ぎ、ペパカフェフォレストの前で、お気楽夫婦が散歩中に偶然出会ったのは、Mr.Dai(ミスター・ダイ)という大道芸人。
 大きなシャボン玉を作ろうとして、なかなか巧く行かなかったのに余裕のミスター・ダイ。「これは人集め。次は巧く行く。次で巧く行かなかったら、晩ご飯抜き」…何かとても楽しそうなキャラクター。余りこの手のパフォーマンスには興味を示さない妻が足を止めた。じっと2人で見入る。次第に彼の周囲に人が集まって来る。「子供たちはここまで前に来て座って♬」用意してあったロープとマットを手際良く並べ、パフォーマンスは続く。なんとか巧く行った巨大シャボン玉の後はジャグリング、輪ゴムなどなどの超絶技巧が続く。「あっ♡そこでオトナがわぁって言ってくれた。嬉しい。今日のお客さまのツボが分かってきた」などと、ことば巧みに惹きつける。いつの間にか妻も私も無防備に笑ってしまっていた。彼のパフォーマンスに引き込まれていた。最前列の子供たちの心からの笑顔も素敵だ。
大きなシャボン玉を作ろうとして、なかなか巧く行かなかったのに余裕のミスター・ダイ。「これは人集め。次は巧く行く。次で巧く行かなかったら、晩ご飯抜き」…何かとても楽しそうなキャラクター。余りこの手のパフォーマンスには興味を示さない妻が足を止めた。じっと2人で見入る。次第に彼の周囲に人が集まって来る。「子供たちはここまで前に来て座って♬」用意してあったロープとマットを手際良く並べ、パフォーマンスは続く。なんとか巧く行った巨大シャボン玉の後はジャグリング、輪ゴムなどなどの超絶技巧が続く。「あっ♡そこでオトナがわぁって言ってくれた。嬉しい。今日のお客さまのツボが分かってきた」などと、ことば巧みに惹きつける。いつの間にか妻も私も無防備に笑ってしまっていた。彼のパフォーマンスに引き込まれていた。最前列の子供たちの心からの笑顔も素敵だ。
 「私、怪しいものではありません。こうやってアートマーケッツの許可証も持ってます。私、これで暮らしてます。お金が貯まったら大学に戻れます。これが終わったらこちらの帽子に…」冗談とシャレを交えて爽やかにチップを促す。「こんな感じのヤツが嬉しいかな…」と空中に四角く紙幣を示す。日本人はチップに慣れがなく、パフォーマンスの相場も分からない。すると近くのベンチで座っていたカップルが千円札を入れた。ウチも千円入れておいで!妻を促す。それ以上の価値があるエンタテインメントだった。満足の千円。次々と帽子の中にチップが入る。良いじゃない!日本も、吉祥寺も。良い街だ。大道芸に対する寛容と許容。自治体などがバックアップして、住民や来街者が応える。良い空間だ。秋の空気と神田川の源流でもある公園の水が創る風景が心地良い。
「私、怪しいものではありません。こうやってアートマーケッツの許可証も持ってます。私、これで暮らしてます。お金が貯まったら大学に戻れます。これが終わったらこちらの帽子に…」冗談とシャレを交えて爽やかにチップを促す。「こんな感じのヤツが嬉しいかな…」と空中に四角く紙幣を示す。日本人はチップに慣れがなく、パフォーマンスの相場も分からない。すると近くのベンチで座っていたカップルが千円札を入れた。ウチも千円入れておいで!妻を促す。それ以上の価値があるエンタテインメントだった。満足の千円。次々と帽子の中にチップが入る。良いじゃない!日本も、吉祥寺も。良い街だ。大道芸に対する寛容と許容。自治体などがバックアップして、住民や来街者が応える。良い空間だ。秋の空気と神田川の源流でもある公園の水が創る風景が心地良い。
「良い街だね」落葉を踏みしめながら妻が呟く。そうだね。じゃあ、鳥良の手羽先でも食べて帰るか!「文脈がどう繋がるか分かんなかったけど、食べて帰ろう!」鳥良は吉祥寺発祥の手羽先の店。お気楽夫婦が通い詰めた初デートの店でもある。井の頭公園を臨むこぢゃれた支店で手羽先にかぶりつく。「美味しい♡」指までしゃぶる妻。住みたい街NO.1だという吉祥寺の魅力を満喫した休日だった。
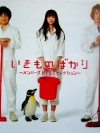 CDが売れないらしい。ミリオンセラーのタイトルが減っている。音楽をレコードやCDというパッケージで購入する時代から、ダウンロードの時代に移行している。かつて、レコードからCDに移行した1980年代は、音源と録音媒体のデジタル化が並行して進行した時代でもあった。デジタル化の夜明け前、聴きたいアルバムを全て買うことはできないから、音質の良いFM放送の番組をカセットテープに録音した(エアチェックと呼ばれていた)。必死に『FM Fan』などのFM情報誌を買って楽曲をチェックしていた。曲の始まるタイミングを計り、息を殺して「REC」ボタンを押していた。ダビングがカンタンにできるダブルカセットのラジカセが人気だった。自分のセレクトした楽曲をオリジナルのベスト盤として編集していた。海岸線をドライブする時、スキーに行く時、彼女がウチに遊びに来た時、などというヴァージョンがあった。…お金はなかったけれど、時間と情熱だけはたっぷりあった。
CDが売れないらしい。ミリオンセラーのタイトルが減っている。音楽をレコードやCDというパッケージで購入する時代から、ダウンロードの時代に移行している。かつて、レコードからCDに移行した1980年代は、音源と録音媒体のデジタル化が並行して進行した時代でもあった。デジタル化の夜明け前、聴きたいアルバムを全て買うことはできないから、音質の良いFM放送の番組をカセットテープに録音した(エアチェックと呼ばれていた)。必死に『FM Fan』などのFM情報誌を買って楽曲をチェックしていた。曲の始まるタイミングを計り、息を殺して「REC」ボタンを押していた。ダビングがカンタンにできるダブルカセットのラジカセが人気だった。自分のセレクトした楽曲をオリジナルのベスト盤として編集していた。海岸線をドライブする時、スキーに行く時、彼女がウチに遊びに来た時、などというヴァージョンがあった。…お金はなかったけれど、時間と情熱だけはたっぷりあった。
 10代の頃に比べれば、時間はないけれど、お金はある。そんなオトナも購入するのがベスト盤CD。気になるアーティストのオリジナルアルバムを買う程ではないけれど、耳に残った=知っている楽曲が入っているベストアルバム。お気楽夫婦のCDラックにも、米米、ポルノ、hitomi、倖田來未、ZARD、一青窈、PRINCES×2、CHEMISTRY、スピッツなどなど、一貫性がないと言われても仕方ないラインナップが並ぶ。そんな2人のライブラリに新たなアーティストのベスト盤が加わった。いきものがかりの『いきものばかり』。正直に言えば、2006年のデビュー曲『SAKURA』は、ちょっとせつなく暗めの曲調が苦手だった。けれど、2008年の『ブルーバード』『気まぐれロマンティック』の明るめの曲調で、あれ?好きな曲かも…となり、2009年の15枚目のシングル『ジョイフル』で、2人揃ってお気に入りのアーティストになった。で、ベスト盤『いきものばかり』だが、…良いアルバムですよ、これ。やはりベスト盤はアーティストを深く知るきっかけであり入口。おススメ。
10代の頃に比べれば、時間はないけれど、お金はある。そんなオトナも購入するのがベスト盤CD。気になるアーティストのオリジナルアルバムを買う程ではないけれど、耳に残った=知っている楽曲が入っているベストアルバム。お気楽夫婦のCDラックにも、米米、ポルノ、hitomi、倖田來未、ZARD、一青窈、PRINCES×2、CHEMISTRY、スピッツなどなど、一貫性がないと言われても仕方ないラインナップが並ぶ。そんな2人のライブラリに新たなアーティストのベスト盤が加わった。いきものがかりの『いきものばかり』。正直に言えば、2006年のデビュー曲『SAKURA』は、ちょっとせつなく暗めの曲調が苦手だった。けれど、2008年の『ブルーバード』『気まぐれロマンティック』の明るめの曲調で、あれ?好きな曲かも…となり、2009年の15枚目のシングル『ジョイフル』で、2人揃ってお気に入りのアーティストになった。で、ベスト盤『いきものばかり』だが、…良いアルバムですよ、これ。やはりベスト盤はアーティストを深く知るきっかけであり入口。おススメ。
 ところで、ベスト盤の中のベストは何かと尋ねられれば、ビートルズの赤盤と青盤!と答える。私にとって初めてのベスト盤であり、ビートルズとの出会いとなった『The Beatles/1962-1966』『 The beatles/1967-1970』だ。ビートルズ解散後の1973年に発売された2枚組。多感な10代だった私にとって、バイブルのようなアルバムだった。誰にとっても繰り返し繰り返し聴いたアルバムがあるはず。いわゆる“すり切れる程”聴いた1枚(2枚組×2セットだけど)だ。赤盤の1曲目デビューシングルの『LOVE ME DO』から、『PLEASE PLEASE ME』『FROM ME TO YOU』『SHE LOVES YOU』…と、このアルバムの収録順に楽曲を覚え、口ずさんだ。青盤の2枚目A面の『BACK IN THE U.S.S.R.』が終わり、一瞬の間の後に「Hey! Ya!」というジョンの掛け声と共に始まるピアノソロ、ゲストミュージシャンとしてギターソロを演奏したエリック・クラプトンの泣きのギターが大好きだった。その後、ほぼ全てのオリジナルアルバムを購入したけれど、このアルバムは別格。10代の頃の記憶も一緒に刻まれている1枚(2枚組×2セットだけど)。
ところで、ベスト盤の中のベストは何かと尋ねられれば、ビートルズの赤盤と青盤!と答える。私にとって初めてのベスト盤であり、ビートルズとの出会いとなった『The Beatles/1962-1966』『 The beatles/1967-1970』だ。ビートルズ解散後の1973年に発売された2枚組。多感な10代だった私にとって、バイブルのようなアルバムだった。誰にとっても繰り返し繰り返し聴いたアルバムがあるはず。いわゆる“すり切れる程”聴いた1枚(2枚組×2セットだけど)だ。赤盤の1曲目デビューシングルの『LOVE ME DO』から、『PLEASE PLEASE ME』『FROM ME TO YOU』『SHE LOVES YOU』…と、このアルバムの収録順に楽曲を覚え、口ずさんだ。青盤の2枚目A面の『BACK IN THE U.S.S.R.』が終わり、一瞬の間の後に「Hey! Ya!」というジョンの掛け声と共に始まるピアノソロ、ゲストミュージシャンとしてギターソロを演奏したエリック・クラプトンの泣きのギターが大好きだった。その後、ほぼ全てのオリジナルアルバムを購入したけれど、このアルバムは別格。10代の頃の記憶も一緒に刻まれている1枚(2枚組×2セットだけど)。
 この秋、その2枚組×2セットがリマスター音源盤で発売された。涙目になりながら即購入。発売された時と同じ(サイズは違うけれど)紙のジャケット。同じ場所で4人が写真に収まっているジャケットデザインも一緒。アップルレコードのA面:Apple、B面:Cut Appleのデザインも一緒。涙。そんな涙したオヤジが多かったらしく、赤盤、青盤ともオリコン・アルバムランキングで上位を獲得。そして、11月17日“Apple”のi-Tunesで、ビートルズの楽曲デジタル配信開始。配信早々のi-Tunesアルバムのチャート1位は赤盤。さすが!その上、ベスト20の中に10作品が入り、4位には『The Beatles Box Set』23,000円!がランク入り。購入した層が目に浮かぶ。
この秋、その2枚組×2セットがリマスター音源盤で発売された。涙目になりながら即購入。発売された時と同じ(サイズは違うけれど)紙のジャケット。同じ場所で4人が写真に収まっているジャケットデザインも一緒。アップルレコードのA面:Apple、B面:Cut Appleのデザインも一緒。涙。そんな涙したオヤジが多かったらしく、赤盤、青盤ともオリコン・アルバムランキングで上位を獲得。そして、11月17日“Apple”のi-Tunesで、ビートルズの楽曲デジタル配信開始。配信早々のi-Tunesアルバムのチャート1位は赤盤。さすが!その上、ベスト20の中に10作品が入り、4位には『The Beatles Box Set』23,000円!がランク入り。購入した層が目に浮かぶ。
CDが売れないのは、音楽が売れないのではなく、音楽配信化されただけではなく、魅力あるアーティストがいないからだけでもなく、“きっかけ”がないだけでもある。身近に音のある生活は“楽”しい。ベスト盤という“きっかけ”でも良い、ずっと音楽が傍らにあって欲しい。「でね、もうCDがラックに入らないんだけど」と怒り気味の妻。そう、デジタル化は収納の悩みがある男を救い、同時にコレクターとしての男を滅ぼす。あぁ…(涙)。

 武蔵野市吉祥寺。情報誌が実施する「住みたい街」アンケートでトップランキングの常連となる街。井の頭公園付近をはじめとした武蔵野の緑と水のある環境や、充実した商業施設、飲食店、そのバランスの良さが人気の理由。吉祥寺は今、ロンロンがアトレに名前を変えリニューアルオープンしたり、伊勢丹吉祥寺店が撤退した後にcoppice KICHIJOJI(コピス吉祥寺)というショッピングビルが誕生したりと何かと話題。中央線沿線の街の中で、立川に逆転された街の集客力を高めるために街をあげて取り組んでいる。老舗焼鳥屋「いせや」の建替えも終わり営業再開。ハーモニカ横町も一時の停滞から小規模立ち飲み店が増え賑わいを取り戻した。
武蔵野市吉祥寺。情報誌が実施する「住みたい街」アンケートでトップランキングの常連となる街。井の頭公園付近をはじめとした武蔵野の緑と水のある環境や、充実した商業施設、飲食店、そのバランスの良さが人気の理由。吉祥寺は今、ロンロンがアトレに名前を変えリニューアルオープンしたり、伊勢丹吉祥寺店が撤退した後にcoppice KICHIJOJI(コピス吉祥寺)というショッピングビルが誕生したりと何かと話題。中央線沿線の街の中で、立川に逆転された街の集客力を高めるために街をあげて取り組んでいる。老舗焼鳥屋「いせや」の建替えも終わり営業再開。ハーモニカ横町も一時の停滞から小規模立ち飲み店が増え賑わいを取り戻した。 お気楽夫婦の住む街から吉祥寺までは、バスでのんびり30分程。マンションの窓から吉祥寺駅周辺のビル群が見える程の距離。ある週末、2人は井の頭公園の紅葉見物に出かけた。井の頭公園は正式名称「井の頭恩賜公園」。大正6年に開園した日本で初めての郊外型公園だと言う。2017年に開園100周年を迎えるに当たって、武蔵野市をはじめとした行政や市民及び関係団体が集まり、井の頭恩賜公園100年実行委員会を設置。その事業の一環として2008年より「井の頭公園アートマーケッツ(ART*MRT)」を実施している。大道芸人やパフォーマーに登録してもらい、土日の公園敷地内でパフォーマンスを行ってもらおうというもの。七井橋を渡りボート乗り場を行き過ぎ、ペパカフェフォレストの前で、お気楽夫婦が散歩中に偶然出会ったのは、Mr.Dai(ミスター・ダイ)という大道芸人。
お気楽夫婦の住む街から吉祥寺までは、バスでのんびり30分程。マンションの窓から吉祥寺駅周辺のビル群が見える程の距離。ある週末、2人は井の頭公園の紅葉見物に出かけた。井の頭公園は正式名称「井の頭恩賜公園」。大正6年に開園した日本で初めての郊外型公園だと言う。2017年に開園100周年を迎えるに当たって、武蔵野市をはじめとした行政や市民及び関係団体が集まり、井の頭恩賜公園100年実行委員会を設置。その事業の一環として2008年より「井の頭公園アートマーケッツ(ART*MRT)」を実施している。大道芸人やパフォーマーに登録してもらい、土日の公園敷地内でパフォーマンスを行ってもらおうというもの。七井橋を渡りボート乗り場を行き過ぎ、ペパカフェフォレストの前で、お気楽夫婦が散歩中に偶然出会ったのは、Mr.Dai(ミスター・ダイ)という大道芸人。 大きなシャボン玉を作ろうとして、なかなか巧く行かなかったのに余裕のミスター・ダイ。「これは人集め。次は巧く行く。次で巧く行かなかったら、晩ご飯抜き」…何かとても楽しそうなキャラクター。余りこの手のパフォーマンスには興味を示さない妻が足を止めた。じっと2人で見入る。次第に彼の周囲に人が集まって来る。「子供たちはここまで前に来て座って♬」用意してあったロープとマットを手際良く並べ、パフォーマンスは続く。なんとか巧く行った巨大シャボン玉の後はジャグリング、輪ゴムなどなどの超絶技巧が続く。「あっ♡そこでオトナがわぁって言ってくれた。嬉しい。今日のお客さまのツボが分かってきた」などと、ことば巧みに惹きつける。いつの間にか妻も私も無防備に笑ってしまっていた。彼のパフォーマンスに引き込まれていた。最前列の子供たちの心からの笑顔も素敵だ。
大きなシャボン玉を作ろうとして、なかなか巧く行かなかったのに余裕のミスター・ダイ。「これは人集め。次は巧く行く。次で巧く行かなかったら、晩ご飯抜き」…何かとても楽しそうなキャラクター。余りこの手のパフォーマンスには興味を示さない妻が足を止めた。じっと2人で見入る。次第に彼の周囲に人が集まって来る。「子供たちはここまで前に来て座って♬」用意してあったロープとマットを手際良く並べ、パフォーマンスは続く。なんとか巧く行った巨大シャボン玉の後はジャグリング、輪ゴムなどなどの超絶技巧が続く。「あっ♡そこでオトナがわぁって言ってくれた。嬉しい。今日のお客さまのツボが分かってきた」などと、ことば巧みに惹きつける。いつの間にか妻も私も無防備に笑ってしまっていた。彼のパフォーマンスに引き込まれていた。最前列の子供たちの心からの笑顔も素敵だ。 「私、怪しいものではありません。こうやってアートマーケッツの許可証も持ってます。私、これで暮らしてます。お金が貯まったら大学に戻れます。これが終わったらこちらの帽子に…」冗談とシャレを交えて爽やかにチップを促す。「こんな感じのヤツが嬉しいかな…」と空中に四角く紙幣を示す。日本人はチップに慣れがなく、パフォーマンスの相場も分からない。すると近くのベンチで座っていたカップルが千円札を入れた。ウチも千円入れておいで!妻を促す。それ以上の価値があるエンタテインメントだった。満足の千円。次々と帽子の中にチップが入る。良いじゃない!日本も、吉祥寺も。良い街だ。大道芸に対する寛容と許容。自治体などがバックアップして、住民や来街者が応える。良い空間だ。秋の空気と神田川の源流でもある公園の水が創る風景が心地良い。
「私、怪しいものではありません。こうやってアートマーケッツの許可証も持ってます。私、これで暮らしてます。お金が貯まったら大学に戻れます。これが終わったらこちらの帽子に…」冗談とシャレを交えて爽やかにチップを促す。「こんな感じのヤツが嬉しいかな…」と空中に四角く紙幣を示す。日本人はチップに慣れがなく、パフォーマンスの相場も分からない。すると近くのベンチで座っていたカップルが千円札を入れた。ウチも千円入れておいで!妻を促す。それ以上の価値があるエンタテインメントだった。満足の千円。次々と帽子の中にチップが入る。良いじゃない!日本も、吉祥寺も。良い街だ。大道芸に対する寛容と許容。自治体などがバックアップして、住民や来街者が応える。良い空間だ。秋の空気と神田川の源流でもある公園の水が創る風景が心地良い。