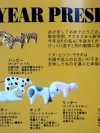ロックの季節・年越しライブ「PANTA」
2010年 1 月10日(日)
 70年代の終わりから80年代の初め、新年の始まりは浅草で迎えていた。浅草寺に初詣に行っていた、訳ではなく「ニューイヤー ロックフェス」という年越しロックイベントで新年を迎えるのが恒例だった。当時は(今はなくなってしまった)浅草国際劇場で開催されていた、大晦日から元旦の朝までのロングライブ。毎年女の子を誘って、ビールを飲みながら夜通し声を上げ、こぶしを振り上げて迎えた新年。ある年は、一緒に行った女の子の母親が作ってくれたお節料理(重箱に入った)を持ち込んで、会場で食べながら迎えた。涙が出る程嬉しくて、美味しかったのだけれど、途中休憩で席を外した途端に重箱ごと盗まれてしまい、涙が出る程哀しかった。そんなたっぷりの記憶と共に思い出す・・・ん、思い出せない(汗)出演アーティスト。そこでググって驚いた。正確に出演者が分かるのだ!ネットワーク社会に感謝。
70年代の終わりから80年代の初め、新年の始まりは浅草で迎えていた。浅草寺に初詣に行っていた、訳ではなく「ニューイヤー ロックフェス」という年越しロックイベントで新年を迎えるのが恒例だった。当時は(今はなくなってしまった)浅草国際劇場で開催されていた、大晦日から元旦の朝までのロングライブ。毎年女の子を誘って、ビールを飲みながら夜通し声を上げ、こぶしを振り上げて迎えた新年。ある年は、一緒に行った女の子の母親が作ってくれたお節料理(重箱に入った)を持ち込んで、会場で食べながら迎えた。涙が出る程嬉しくて、美味しかったのだけれど、途中休憩で席を外した途端に重箱ごと盗まれてしまい、涙が出る程哀しかった。そんなたっぷりの記憶と共に思い出す・・・ん、思い出せない(汗)出演アーティスト。そこでググって驚いた。正確に出演者が分かるのだ!ネットワーク社会に感謝。
 ちなみに、この内田裕也プレゼンツのイベントは現在も会場や形態を変えて継続開催中。銀座博品館劇場で開催された2009-2010で37回目だという。私が行った1979-1980 7thの主な参加アーティストは、ダウンタウンブギウギバンド、桑名正博&Tear Drops、柳ジョ−ジ&レイニーウッド、ジョニー大倉 & VACATION CLUB、アン・ルイス&ブラッドショット、力也 & CROCODILE、BORO、ヒカシュー、RCサクセション、SHEENA & THE ROKKETS、ハウンド・ドッグなど錚々たるメンバー。そして、1980-1981には前年の主要メンバーに加え、PANTA&HAL、シャネルズ、上田正樹、BORO、白竜、めんたんぴん、J.WALK、もんた&ブラザース、ザ・ロッカーズ、萩原健一、松田優作 &エディ藩グループなどの名前が。今思い返せば、落涙もの。ロックの季節だった。
ちなみに、この内田裕也プレゼンツのイベントは現在も会場や形態を変えて継続開催中。銀座博品館劇場で開催された2009-2010で37回目だという。私が行った1979-1980 7thの主な参加アーティストは、ダウンタウンブギウギバンド、桑名正博&Tear Drops、柳ジョ−ジ&レイニーウッド、ジョニー大倉 & VACATION CLUB、アン・ルイス&ブラッドショット、力也 & CROCODILE、BORO、ヒカシュー、RCサクセション、SHEENA & THE ROKKETS、ハウンド・ドッグなど錚々たるメンバー。そして、1980-1981には前年の主要メンバーに加え、PANTA&HAL、シャネルズ、上田正樹、BORO、白竜、めんたんぴん、J.WALK、もんた&ブラザース、ザ・ロッカーズ、萩原健一、松田優作 &エディ藩グループなどの名前が。今思い返せば、落涙もの。ロックの季節だった。
 そこにお目当てのバンドがいた。PANTA & HAL。伝説のバンド「頭脳警察」のヴォーカル、PANTAが率いるロックバンドだ。1975年に頭脳警察は解散。その解散ライブを行った屋根裏(西武の隣にあった)で、初めてPANTAを聴いた時の衝撃。以降、彼の出演するライブを観まくった。「世界革命宣言」「銃をとれ」「ふざけるんじゃねぇよ」などと過激なタイトルに現れるように、極めてラジカルだった。1971年の日劇ウェスタンカーニバルでのステージはパフォーマンスとしても極めてラジカルで、伝説になっていた。それから10年近く経ったその当時、依然として“かっこ良かった”。「マラッカ」「つれなのふりや」の煽るようなハードなナンバーも。「裸にされた街」の引き絞るようなバラードも。決して巧くはない、けれど華があった。過激なオーラがあった。いつもエネルギーの塊のようなステージだった。
そこにお目当てのバンドがいた。PANTA & HAL。伝説のバンド「頭脳警察」のヴォーカル、PANTAが率いるロックバンドだ。1975年に頭脳警察は解散。その解散ライブを行った屋根裏(西武の隣にあった)で、初めてPANTAを聴いた時の衝撃。以降、彼の出演するライブを観まくった。「世界革命宣言」「銃をとれ」「ふざけるんじゃねぇよ」などと過激なタイトルに現れるように、極めてラジカルだった。1971年の日劇ウェスタンカーニバルでのステージはパフォーマンスとしても極めてラジカルで、伝説になっていた。それから10年近く経ったその当時、依然として“かっこ良かった”。「マラッカ」「つれなのふりや」の煽るようなハードなナンバーも。「裸にされた街」の引き絞るようなバラードも。決して巧くはない、けれど華があった。過激なオーラがあった。いつもエネルギーの塊のようなステージだった。
 そんな季節を忘れてしまっていた。年越し蕎麦を啜りながら、紅白歌合戦をのんびりと眺めながら、過ごす大晦日の夜。あんな季節を過ごしていた自分を忘れてしまっていた。音楽はBGMとして聴いている自分を自覚していた。ところがある日、忘れていたライブの興奮を久しぶりに思い出させる夜(詳しくは明日の記事で)を過ごした。そしてその記事をすぐに書く前に、書いておきたいことがあったと思い出した。それがPANTAだった。CDコレクションの奥にあったPANTAのアルバムを探して聴いてみた。「TKO NIGHT LIGHT」という1980年のライブアルバム。書斎に籠り、リビングにいる妻に聞こえないようにドアを閉める。音量を上げる。あの季節と変わらないPANTAが現れた。そして名曲「マーラーズ・パーラー’80」を聴いた瞬間に、私の身体が時空を超えた。こぶしを振り上げ、涙が零れそうになる。
そんな季節を忘れてしまっていた。年越し蕎麦を啜りながら、紅白歌合戦をのんびりと眺めながら、過ごす大晦日の夜。あんな季節を過ごしていた自分を忘れてしまっていた。音楽はBGMとして聴いている自分を自覚していた。ところがある日、忘れていたライブの興奮を久しぶりに思い出させる夜(詳しくは明日の記事で)を過ごした。そしてその記事をすぐに書く前に、書いておきたいことがあったと思い出した。それがPANTAだった。CDコレクションの奥にあったPANTAのアルバムを探して聴いてみた。「TKO NIGHT LIGHT」という1980年のライブアルバム。書斎に籠り、リビングにいる妻に聞こえないようにドアを閉める。音量を上げる。あの季節と変わらないPANTAが現れた。そして名曲「マーラーズ・パーラー’80」を聴いた瞬間に、私の身体が時空を超えた。こぶしを振り上げ、涙が零れそうになる。
「ふぅ〜ん」妻が関心なさそうに記事を読んでいる。「かぐや姫にいた人とは違うんだよね」はい、それは山田パンダですし。読書傾向だけではなく、妻と私の音楽嗜好も微妙に違う。